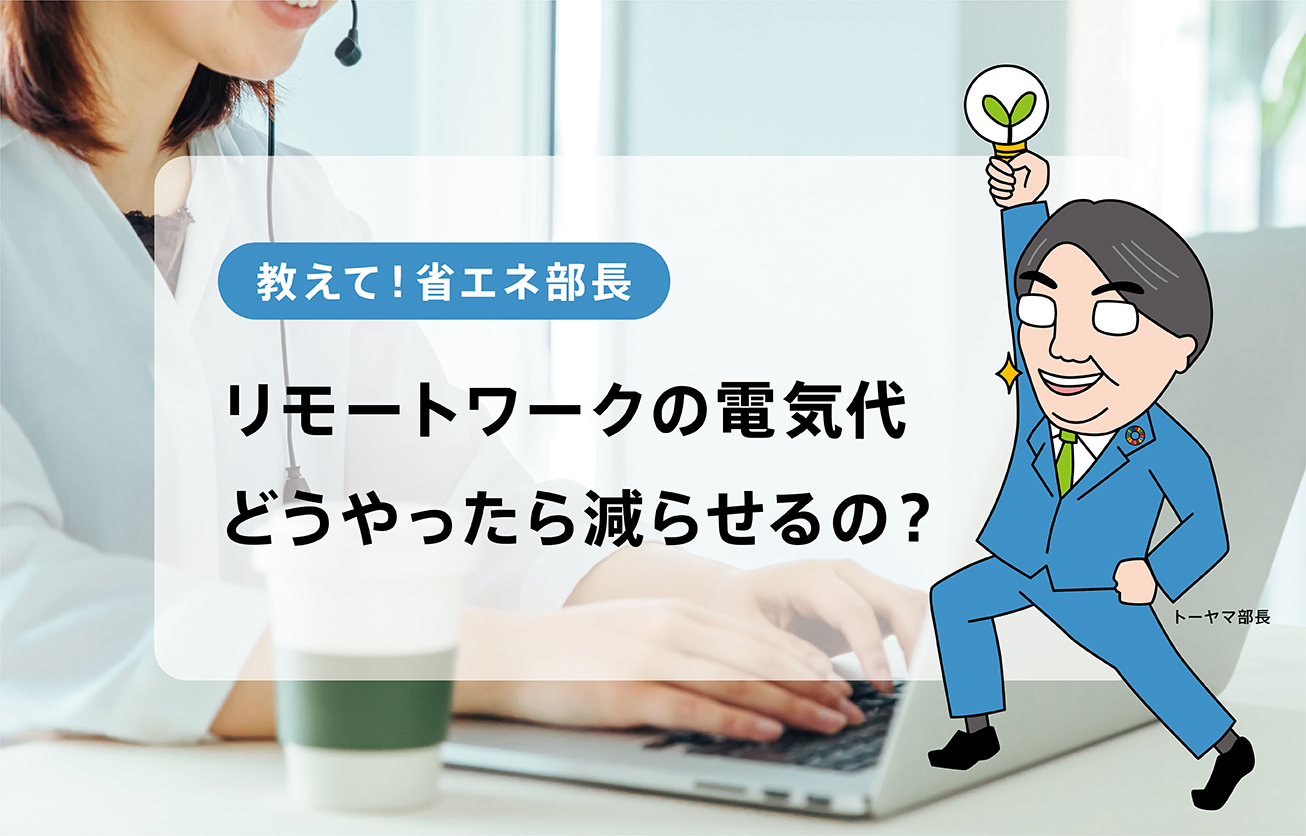インターナルカーボンプライシング(ICP)とは?仕組みをわかりやすく解説
気候変動問題への対策、カーボンニュートラルの実現に向けて、企業における脱炭素の取り組みが広がっています。その中でも、企業内で脱炭素投資を推進するために不可欠な仕組みとして注目されているのが「インターナルカーボンプライシング(ICP)」です。
本記事では、インターナルカーボンプライシングの概要や導入のメリット、価格設定の考え方などについて解説いたします。
インターナルカーボンプライシング(ICP)とは?

インターナルカーボンプライシング(ICP)とは、企業が脱炭素を推進するために、独自にCO2排出量に価格を付けて、投資判断等に活用する仕組みです。カーボンプライシングの方法の一つとされています。
特にCO2排出量削減など気候変動に関する目標を掲げている企業において、単純な経済性の観点から、投資回収が可能な施策だけを実施するのでは削減目標の達成が難しくなります。そのためICPは、CO2排出量に対して価格を付けることで、排出コストとして金額換算し、脱炭素投資を推進するインセンティブを生み出すことや、脱炭素に関連する収益機会とリスクを特定することをねらいとして導入されます。
脱炭素の投資へのインセンティブとは、例えば、使用する電力についてA案とB案を検討するとします。下図のようにCO2排出量が少ない選択肢A案とCO2排出量が多い選択肢B案について意思決定をする際、ICPを導入することで脱炭素の観点も考慮して判断することが可能となります。通常のコストのみによる判断であればB案が選択されるケースであっても、ICPを導入した場合その価格設定次第では、A案が選択されるようになります。

インターナルカーボンプライシング(ICP)の仕組み
インターナルカーボンプライシング(ICP)は、企業が独自に炭素価格を設定できるため、社会の動向に応じて価格を変更することが可能です。脱炭素の取り組みが国内企業で盛んな時期には、価格を上げて気候変動対策を推進することができます。逆に、脱炭素の動きが落ち着いた時には、通常の価格に戻すなど、柔軟な対応ができます。
インターナルカーボンプライシング(ICP)導入が求められている背景
深刻化する気候変動問題への対応として、世界では産業革命後の気温上昇を1.5℃に抑えようという「1.5℃目標」を掲げています。その達成のためには、2030年までに二酸化炭素の排出量を2010年比で45%削減し、さらに2050年までに二酸化炭素排出量を正味ゼロ(カーボンニュートラル)にする必要があります。
そのように気温上昇を1.5℃に抑えようとした場合、世界全体として、あとどれだけ排出してもよいかという排出量の上限(カーボンバジェット)が決まります。その上限を超えないためには、排出量に対して価格付けを行うなど、排出量の削減を促す仕組みが不可欠になります。
また、企業に対して気候変動への取り組みに関する質問書を出している「CDP(Carbon Disclosure Project)」ではICPに関する質問項目が設けられていることや、企業に対して気候変動に関する情報開示を推奨する「TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)」においてもICPを低炭素の投資指標として活用することが推奨されています。
このように社会全体としてカーボンニュートラルを達成するために企業活動も変化が必要となっている一方で、外部からの排出量に対する価格付けが十分な水準で行われていない現状であるため、企業が自主的にICPを導入し、脱炭素投資を推進していく必要があると考えられています。
関連記事▷
カーボンバジェットとは?1.5℃目標について分かりやすく解説
インターナルカーボンプライシング(ICP)導入のメリット

企業がICP(インターナルカーボンプライシング)を導入することによるメリットを3つご紹介します。
① 脱炭素投資を推進することができる
短期的な経済性だけにとらわれずに、自社の脱炭素取り組み方針に合わせた意思決定が可能となります。ICPの導入によって社内で明確な基準による価格付けができるようになり、CO2排出量まで考慮した経済性の評価を行えるようになります。
例えば、下図の投資案のイメージのように、投資回収期間の観点で判断をする場合でも、ICPを導入していることで排出量削減の経済性を加味することができ、その投資によって期待できる見かけの収益が増えることから、投資判定基準が引き下がり、脱炭素活動が推進されます。

また、企業として脱炭素目標を掲げている場合、ICPが導入されていなければ、脱炭素に対する投資判断基準がないことに等しくなり、目標は絵に描いた餅となってしまいます。しかし、ICPを導入した場合、目標達成と整合性がとれた脱炭素投資について、費用対効果の高い施策から順に実行していくことも可能です。また、投資判断基準を明確にできることから、「この水準までは実施する」、「この水準からは実施しない」といったかたちで非効率な脱炭素投資を防ぐことにも繋がります。
さらに、先進企業では、各部門の排出量に応じたICPについて実際に資金として社内で回収し、「脱炭素投資ファンド」のような方法で、さらなる再エネ導入やカーボンオフセットなど脱炭素投資に活用するという事例もあります。
② 将来的なリスクや影響を可視化して備えることができる
日本国内においても、炭素税や排出量取引といった方法で政策としてのカーボンプライシング導入が検討されています。企業としてICPをあらかじめ導入することは、将来的にカーボンプライシングが導入された際に、自社の事業活動においてどのぐらいのコスト負担が発生するのか等、その影響を可視化し、先回りして備えることに繋がります。
社会全体として脱炭素への緊急度がさらに高まった場合、カーボンンプライシング等の政策も急速に、より影響の強い内容となる可能性もあり、何も準備しないことは大きな経営リスクに繋がります。
③ ステークホルダーに対して脱炭素の取り組み姿勢を示すことができる
企業は投資家をはじめとしたあらゆるステークホルダーから脱炭素への取り組みに対する要請が強まっています。その期待と責任に対して、ICPという定量的な基準を設定することによって、経済的成果と気候変動対策を両立して取り組んでいる姿勢をアピールすることができます。
脱炭素目標を掲げているにも関わらず、具体的な削減ロードマップの策定や、ICPの導入による投資判断基準の明確化がなされていない場合、外部からはグリーンウォッシュと捉えられてしまうリスクもあります。
※グリーンウォッシュとは、上辺だけ環境配慮をしているように装い、ごまかすこと。
一方で業界内において、いち早くICPを導入することで、目標達成に向けて脱炭素投資の実効性を高めている企業は、ステークホルダーから高い評価を得られる機会があります。
インターナルカーボンプライシング(ICP)の価格設定について
ICPは一般的にCO2排出量1t当たりの価格を設定します。その設定価格は導入の目的や活用方法等によって大きく異なります。実際に世界における各社の事例では10倍以上の差が存在しているといわれています。

引用元:インターナルカーボンプライシング活用ガイドライン|環境省
ICP導入の目的としては、“取り組みの要因(内定・外的)”と“投資行動の緊急度”で整理することができます。
例えば、自社が掲げているSBTやRE100といった脱炭素目標を達成するために脱炭素投資を推進する必要がある場合は内的な要因であり、緊急度も高いと整理できます。また、いつか強化・導入される可能性がある脱炭素規制への準備という目的であれば、外的な要因であり、投資行動の緊急度は低めであると整理できます。

引用元:インターナルカーボンプライシング活用ガイドライン|環境省
ICPの価格設定を行う方法は4種類あります。それぞれの方法で導入の難易度や脱炭素投資の実効性が異なるため、自社のICP導入目的や脱炭素取り組み方針、社内の状況等を踏まえて、取り組みやすい方法を選択する必要があります。
①外部価格の活用
例えば、IEA(International Energy Agency)等の外部による炭素税や排出量取引の炭素価格に関する将来予測を参考に設定する方法です。
②同業他社価格のベンチマーク
例えば、CDPレポート等でICPについて公表している同業他社の価格を参考にして設定する方法です。
③脱炭素投資を促す価格に向けた社内討議
過去の投資案件を振り返り、投資の意思決定が逆転したであろう水準のICP価格を算出して設定する方法です。
④CO2削減目標による数理的な分析
自社で定めている脱炭素目標を達成するために必要な投資を列挙し、その対策にかかる総コスト(円)と累積削減量(t-CO2)から算出する方法です。
ICP(円/t-CO2)=対策総コスト(円)÷累積削減量(t-CO2)

引用元:インターナルカーボンプライシング活用ガイドライン|環境省
また、ICPは一度設定をしたら変更ができないものではなく、外部環境の変化に応じて、柔軟に価格を見直すことが可能です。まずは導入がしやすい設定価格から開始して社内に浸透させ、その後、社内外の状況を踏まえながら運用をしていくという方法も有効と考えられます。
インターナルカーボンプライシング(ICP)の導入状況

日本においては、ICPを導入する企業は増加傾向にあります。2015年は435社でした。しかし、2020年には854社とほぼ倍増している状況です。さらに、2年以内の導入を検討する企業は、2018年以降急増しており、関心度の高さがうかがえます。
世界でみてみると、ICP導入(予定)企業数は主要国アメリカが1位を獲得しており、日本は次いで2位となっています。とはいえ、導入済みの企業と2年以内の導入を検討する企業はそれぞれ10社ほどの違いなので、大きな差があるわけではありません。気候変動による影響が深刻化する昨今、ICPを導入する企業はますます増えるでしょう。
インターナルカーボンプライシング(ICP)導入企業の事例
ICPを導入あるいは導入予定の企業は急増しており、世界では2,000社超、日本企業においては以下のような約280社となっています。

引用元:インターナルカーボンプライシング活用ガイドライン|環境省
国内におけるICP導入企業の一例を紹介します。
アステラス製薬
価格設定:100,000円/t-CO2
インターナルカーボンプライスを投資基準の一つとすることで、低炭素投資を推進
出所:CDP回答(2021)
アステラス製薬では、1トンの二酸化炭素あたりの価格を100,000円に設定しています。運用方法としては、総務本部内の専門チームが炭素市場の社会動向を調査し、価格案を作成します。その案に基づき、経営管理・コンプライアンス担当役員が価格を見直し、その都度設定します。二酸化炭素の削減コストが100,000円を上回る場合は投資が見送られ、下回る場合は投資が実施されます。
花王
価格設定:18,500円/t-CO2
SBT 1.5℃に準じたScope1, 2でのCO2削減目標を設定し、価格を引き上げている
出所: 花王『2021年活動報告 脱炭素』
花王では、2021年までの二酸化炭素1tあたりの価格設定は3,500円でした。しかし、SBTi 1.5℃目標を達成するための設備導入が不可能であることが判明し、18,500円に引き上げられました。省エネ設備の導入によって削減されたCO2排出量の炭素価格、そしてエネルギーコストの合計が、投資基準に反映しています。
キリンホールディングス
価格設定:15,434円/t-CO2
2℃シナリオにおける2040年の温室効果ガス排出量・排出コストを、目標達成・未達の2パターンで試算
出所:CDP回答(2021)
キリンホールディングスはICP導入予定の企業です。温室効果ガスの排出量を削減するとともに、カーボンプライシング導入に伴う減益リスクを軽減するため、投資判断基準の1つとしてICPの導入を決めています。これにより、企業価値の向上を目指しています。
アスクル
価格設定:8,500円/t-CO2
アスクルの「2030年CO2ゼロ」およびSBT目標を達成するために、2030年までにスコープ1、スコープ2およびスコープ3におけるCO2累積削減量をもとに内部炭素価格を設定
出所:CDP回答(2021)
アスクルでは、1トンの二酸化炭素あたりの価格を8,500円に設定しています。運用方法としては、現行の炭素価格を可視化し、ICP価格をSBT(Science Based Targets)に対応させることで、環境投資枠に適用させます。設定したICP価格は、全社の投資判断に利用されます。
当初、ICP導入の取り組みはアスクル単体で行われていましたが、理解と浸透が進んだことで、現在ではグループ企業にも展開されています。
東急不動産ホールディングス
価格設定:6,000円/t-CO2
現在の再エネ調達価格(一般+3円/kWh)を算出根拠として、一律6,000円/t-CO2で価格設定
出所:CDP回答(2021)
東急不動産ホールディングスでは、第1フェーズ(’18~’20)・第2フェーズ(’21~’30)・第3フェーズ(’31~’50)と段階的に導入を進められています。第1フェーズでは、現在の再エネ調達価格(一般+3円/kWh)を算出根拠として、二酸化炭素1tあたりの価格は一律6,000円に設定しています。第2フェーズでは規制強化・中長期目標設定に対応した設定価格の見直し、第3フェーズでは再エネ調達費用に対応した設定価格の見直しがおこなわれる予定です。
富士通
価格設定:1,000円/t-CO2
Jクレジットのレートを参考に価格設定
出所:「インターナルカーボンプライシング活用ガイドライン~企業の脱炭素投資の推進に向けて~(2022年度版)」
富士通では、二酸化炭素1tあたりの価格を1,000円に設定しています。国や地域、部署によって価格の差異がないよう、Jクレジットのレートを参考にすることで統一化。グループ全体の排出量が目標値を超えた場合、各事業部門から超過分に応じて課金を徴収し、省エネ設備への投資などに補填されます。
まとめ
ICPは企業が脱炭素を推進していくためには不可欠な仕組みです。導入に向けたハードルはありますが、ステークホルダーからの期待に応えるため、または、将来的な炭素税といった外部からのカーボンプライシングに備えるためにも、先手を打って導入することが重要といえます。
本記事を参考に、ICPの導入を検討してみてはいかがでしょうか。
▷関連記事
・炭素税とは?メリットやデメリット、日本での現状について簡単に解説!
・カーボンプライシングとは?①〜種類や国内外にもたらす影響について〜【専門家インタビュー】
▷グリラボSNSのフォローお願いします!!
Twitter @gurilabo
▷アイグリッドグループ