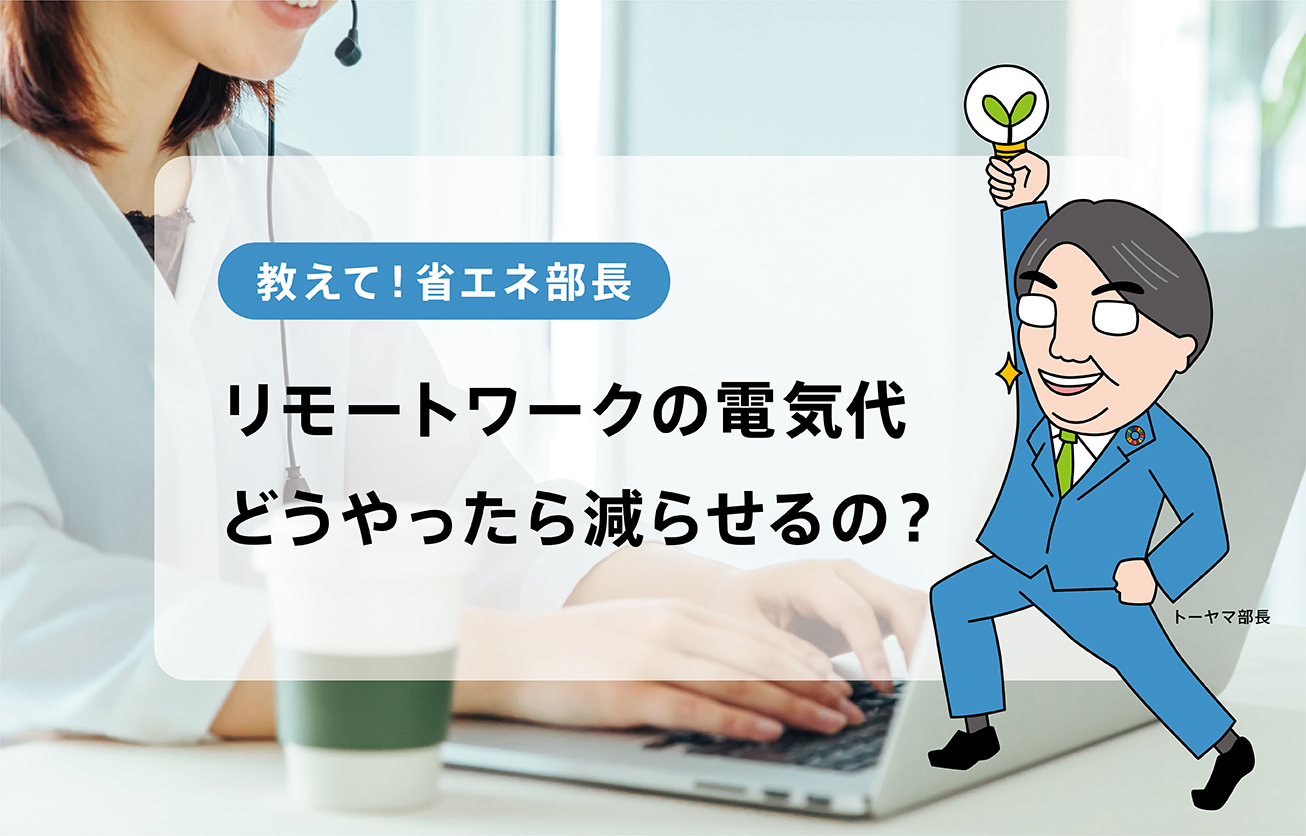日本におけるカーボンプライシングの現状は?与える影響も解説
脱炭素社会を実現するために日本で行われている取り組みのひとつに、カーボンプライシングがあります。名前を聞いたことはあっても、他の制度と混同してよくわからないと困っている人もいるのではないでしょうか。
本記事では、カーボンプライシングの概要やメリット・デメリット、日本におけるカーボンプライシングの現状と今後について解説します。環境活動に興味のある方や、企業の環境部門担当の方などはぜひ参考にしてください。

CO2 tax, Carbon credit. Tree on money with co2 icon on green background. environmental and social responsibility business concept. Taxation for nature pollution. Controlling carbon emission
カーボンプライシングとは?
カーボンプライシングとは、企業が排出するCO2に値付けをし、排出量に対して金銭的な負担を課す制度です。カーボンプライシングは企業活動におけるCO2排出量の削減を狙いとして、世界各国で導入されています。
カーボンプライシングのメリット
カーボンプライシングによって、企業の温室効果ガス削減の取り組みを促進することが期待できます。脱炭素への取り組みに多くの企業が着手すれば、地球全体の温室効果ガスを削減することにつながるでしょう。
また、企業が脱炭素対策に積極的に取り組むことは、多くの脱炭素技術が生まれることにつながります。開発された製品やサービスの価値が向上すれば、資金調達が有利になるなどの好循環が生まれ、脱炭素技術のさらなる拡大も期待できます。
国にとって、財源を確保しながらカーボンニュートラルの達成を目指せる点もメリットのひとつといえるでしょう。
カーボンプライシングのデメリット
カーボンプライシングの導入には、カーボンリーケージや企業コスト増大などのデメリットが発生するおそれがあります。
カーボンリーケージとは、自国の企業がCO2の排出規制から逃れるために、規制の緩い他国に生産拠点を移すことです。カーボンリーケージが発生すれば、日本におけるCO2排出量を削減できても、地球全体のCO2削減にはならず、本来の目的を達成できません。また、日本経済に悪影響を及ぼす可能性もあるでしょう。
企業にとっては、コストが増加することも問題です。特に、運輸業や製造業などCO2排出量がもともと多い産業においては、カーボンプライシングによって活動が制限され、売上減少や国際競争力の低下につながることも懸念されます。
日本におけるカーボンプライシングの導入状況
カーボンプライシングは世界各国で採用されている制度ですが、日本での導入状況はどうなのでしょうか。これまでに行われてきた取り組みと、今後導入予定の取り組みを解説します。
2012年10月に「地球温暖化対策のための税」を導入
日本では、2012年10月に実質的なカーボンプライシングである「地球温暖化対策のための税」を導入しました。
「地球温暖化対策のための税」は、1トンあたりのCO2排出量に対し、289円を企業が税として負担する仕組みです。この税は化石燃料に対して課されるため、化石燃料の輸入者のほか、化石燃料を使用する消費者や事業者も間接的に税を負担します。
税額は導入当初から徐々に引き上げられ、2016年に現在の289円になりました。ただし、289円という税額はヨーロッパ諸国と比較すると大幅に低い金額であることから、ほかの方法で税金を課すことが検討されています。詳しくは次の項で解説します。
2028年度頃から炭素賦課金と排出権取引の2つを導入予定
日本では2023年にGX推進法が施行され、新たなカーボンプライシングの手法として、今後「炭素賦課金」と「排出権取引」の導入が検討されています。それぞれの概要を以下に解説します。
炭素賦課金
炭素賦課金とは、CO2などの温室効果ガス排出量に対して賦課金を課すカーボンプライシングの手法のひとつです。賦課金は特定の活動に対して負担する金銭を指し、税金とは異なります。そのため金額の調整が可能で、国の目標や経済状況に応じて政策を変更しやすいことが特徴です。
炭素賦課金は、2028年より化石燃料の輸入企業を対象に導入することが予定されています。価格は既存の賦課金や税金の動向によって左右されるため、2025年時点では未定ですが、1トンあたり2,000円前後になるという見方もあります。
炭素賦課金を導入することで、企業の低炭素化への取り組みがさらに加速することが期待できるでしょう。企業のコスト負担は増えるものの、脱炭素への取り組みが投資家や消費者から評価されれば、売上向上につなげることも可能です。
また、日本政府においては炭素賦課金で得た収入を再生可能エネルギーの普及などに活用でき、2050年のカーボンニュートラルに向けた対策がしやすくなります。
排出権取引(GX-ETS)
排出権取引とは、国や企業ごとに温室効果ガス排出の枠を設け、枠を超えてしまった場合は他国や他企業から排出枠を購入できる制度です。排出量取引とも呼ばれます。
排出権取引では、CO2排出量の削減が難しい企業でも、排出枠を購入することで容易に削減を達成できます。CO2の排出枠を取引して排出量をフラットにすることで、地球全体の温室効果ガス排出量を削減することが狙いです。
現状では、ヨーロッパ諸国やカナダ、中国が導入しており、日本では東京都や埼玉県が個別に導入しています。日本では2026年度から本格稼働、2033年からは更に発展させた稼働を行うと発表しており、準備が進められています。
排出権取引は、販売する側の収益増加につながることもメリットです。温室効果ガスを削減すればするほど販売額も上がるため、CO2排出を抑える施策に対してのモチベーションが向上しやすいでしょう。
日本にカーボンプライシングが導入されるとどんな影響がある?
日本でのカーボンプライシング導入は、企業にとってCO2排出量削減にこれまで以上に積極的に取り組むきっかけになると考えられます。また、政府にとっては脱炭素に向けた投資の加速につながるため、国全体で脱炭素への意識を高められるでしょう。
一方で、企業はエネルギーコストの増加によって経営に大きな影響が出る可能性があります。特に、発電業や製造業などエネルギーを多く使う産業は、エネルギーの使用を削減するための工夫が必要となるでしょう。
企業のエネルギーコストの上昇は、製品の価格にも反映されます。カーボンプライシングの導入によって、消費者が購入する電力や製品の価格も上昇する可能性が高まっています。
関連する制度もチェック
カーボンプライシングのほかに、CO2排出を取引する制度を2つ紹介します。
インターナルカーボンプライシング
インターナルカーボンプライシングとは、国や自治体ではなく、企業が独自にCO2排出量に価格をつける制度です。企業が自社におけるCO2排出量を可視化することで、社内の脱炭素への意識を高めたり、目標設定をしやすくしたりする狙いがあります。
インターナルカーボンプライシングの価格設定には、企業がどの程度CO2排出削減に力を入れているかが反映されます。自社の価格設定によっては投資家から注目され、脱炭素投資の機会を増やすことも可能です。
近年では、環境問題や社会問題への取り組みを積極的に行う企業が投資判断の際に評価されやすい傾向にあります。その点で、インターナルカーボンプライシングは投資家へのアピールにも有効です。
民間セクターによるクレジット取引
民間セクターによるクレジット取引とは、政府の規制とは関係なく、企業間や市場で取引されるカーボンクレジットのことです。民間セクターによるクレジット取引の例としては、ボランタリークレジットが挙げられます。
ボランタリークレジットは民間やNGOが主導するため、国が主導するクレジット取引と比較して制約が少ないことが特徴です。また、クレジットの種類が豊富であり、例えば水質保全や森林保全、CO2回収技術、雇用創出など、さまざまなクレジット創出が可能な点も使いやすいポイントといえます。
ただし、ボランタリークレジットは法的拘束力がないため公的な報告には利用できないことがほとんどです。国際イニシアチブへの報告に活用したい場合は、Jクレジットやグリーン電力証書などの利用が一般的といえます。
日本が目標とする2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、ボランタリークレジットは市場で急速に拡大しつつあります。クレジット取引によるカーボンオフセットを実現したい企業は、選択肢のひとつとして検討してみると良いでしょう。
できることから脱炭素を進めよう
今後、日本でも本格的なカーボンプライシングが導入されます。カーボンプライシングによって環境対策への意識が高まりやすくなる一方で、企業にとってはコスト増大の影響も無視できません。省エネ設備の導入や資金調達先の確保など、できることから早めの対策を打っておきましょう。
アイ・グリッド・ソリューションズでは、再生可能エネルギーの導入による低炭素化への取り組みを後押ししています。CO2排出量削減のために自社でできることはないかと模索している経営者や企業担当者は、ぜひご相談ください。
▷関連記事
・温室効果ガスを減らすには?企業や個人がすぐに始められることを紹介
・カーボンクレジットとは?海外や日本での取り組みを含めわかりやすく解説
▷アイ・グリッド・ソリューションズ関連はこちらをチェック