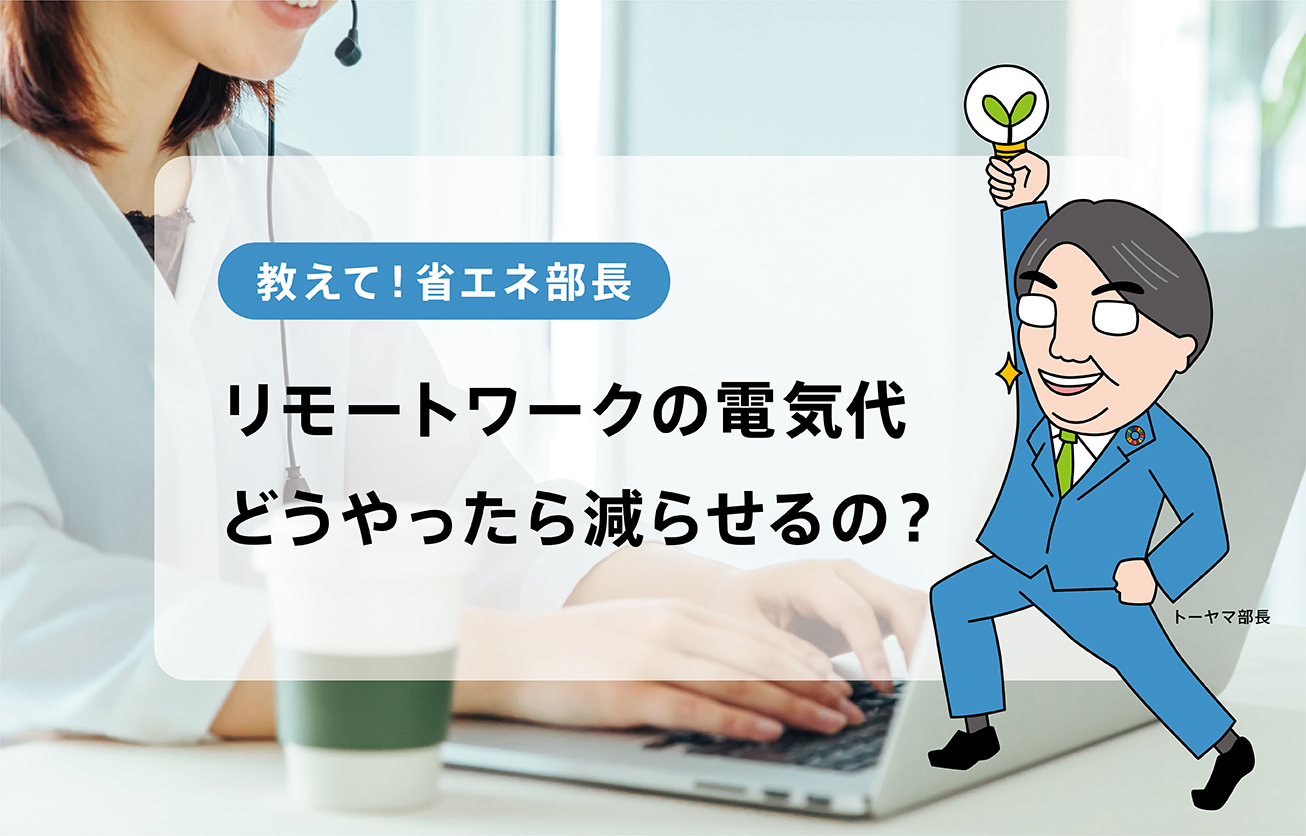「電気が足りない?!」EV普及で家と地域のエネルギーを見直す訳【専門家コラム②】
脱炭素社会に向けて徐々に普及しているEV(電気自動車)。前回に続いて今回もモビリティ―ジャーナリストである楠田悦子さんにEVをテーマに執筆を依頼しました。
前回の記事はこちら。
 楠田悦子/モビリティジャーナリスト
楠田悦子/モビリティジャーナリスト心豊かな暮らしと社会のための、移動手段・サービスの高度化・多様化と環境について考える活動を行っている。自動車新聞社モビリティビジネス専門誌『LIGARE』初代編集長を経て、2013年に独立。国土交通省の「自転車の活用推進に向けた有識者会議」、「交通政策審議会交通体系分科会第15回地域公共交通部会」、「MaaS関連データ検討会」、SIP第2期自動運転(システムとサービスの拡張)ピアレビュー委員会などの委員を歴任。共著に最新 図解で早わかり MaaSがまるごとわかる本 、編著に「「移動貧困社会」からの脱却: 免許返納問題で生まれる新たなモビリティ・マーケット」(時事通信社)
「省エネ・節電にご協力ください」
2022年は電力不足、価格の高騰など、当たり前にあると思っていた生活に欠かせない電気や燃料において、不安がつきまとった年でした。需要変動への対応やロシアのウクライナ進行により、国際的な燃料の価格高騰などが原因だといいます。
このような中、電気を使う電気自動車(EV)を使うことに、矛盾を感じる人も多いのではないでしょうか?
▼エネルギー自給率はわずか12.1%
資源エネルギー庁によると、日本のエネルギーは海外から輸入される石油・石炭・天然ガス(LNG)など化石燃料に大きく依存しています。東日本震災以降、原子力発電が11.2%(2010年度)から2.8%(2019年度)に落ちたため、化石燃料への依存が81.2%(2010年度)から84.8%(2019年度)へと高まっています。2020年の主な化石燃料輸入先は、財務省貿易統計によるとサウジアラビヤ(40.1%)、アラブ首長国連邦(31.6%)などの中東からです。
2019年度の日本のエネルギー自給率はわずか12.1%と、他のOECDに比べて低い水準にあります。このようにみてみると、日常的に使っている電気やガソリンを使って走る自動車のエネルギーそのもの根源的な問題は同じで、見直して必要があることがわかります。
実は今年も改めて、私たちは国内での石油、石炭、天然ガスの産出が難しいため、原子力発電を除けば、地熱、風力、太陽光などの再生可能エネルギーで、エネルギーを確保していく必要があることを身に染みて体験したことになります。
▼エネルギーを自給自足(家で電気を作って、EVにためて、使う)
もっとも国際情勢や電力会社の影響を受けずに、電気エネルギーを調達する方法は、自宅に設置した太陽光発電でつくった電気をEVにため、EVから家に給電して使う、エネルギーの自給自足だといいます。たとえば、日産自動車によると、40kWh/62kWhのバッテリーを備えた日産リーフ(ZE1型)は、一般家庭の約2から4日分の電力をまかなうことができます。小規模の集合住宅などでも、自給自足をする建物として付加価値に着目されるようになるでしょう。


▼東日本大震災を振り返る
2011年の東日本大震災の際に、被災地の電力確保、首都圏の規模な計画停電により、分散型エネルギーシステムが日本にとって喫緊の課題となりました。この時期は、ちょうど電気自動車や太陽光発電の普及が注力され、エネルギーの地産地消やスマートシティが着目された頃でもあります。
今デジタル社会のキーワードの一つとなっている「スマートシティ」は、その当時デジタルではなく、電気エネルギーに着目していて、“スマートコミュニティ”と言われていました。コミュニティ単位で、分散型エネルギーをITや蓄電池などを活用したエネルギーマネジメントシステム(EMS)を通じて、分散型エネルギーシステムによるエネルギー需給を総合的に管理・最適化するというものです。
スマートコミュニティはEVと都市、EVと家、EVとビルがつなげて、より良い暮らしや社会を実現することを目指していました。キーワードとして、ホームマネジメントシステム(HEMS)、ブイツーエイチ(V2H)、ビルマネジメントシステム(BEMS)、地域エネルギーマネジメントシステム(CEMS)などがありました。
▼新たな動き
電気エネルギーに関する取り組みは一段落していました。しかし、新たな動きが出てきています。
神奈川県の小田原市は、2019年に市内で、EVを活用したカーシェアリング事業を行うレクシヴ(REXEV)社や地域新電力である湘南電力と連携して、「小田原市EVを活用した地域エネルギーマネジメントモデル事業」と締結しました。
また北陸電力(富山県富山市)は電気自動車、充電設備、エネルギーマネジメントシステム&車両管理システムを顧客毎にサービス内容をカスタマイズして提供しています。
2022年においては、日本郵便は、東京大学発ベンチャーのヤネカラ社(Yanekara、千葉県柏市)とともに「集配用 EV 車両の効率的な充電によるエネルギーマネジメント実証実験」を開始しました。
さらに、国内初の大規模な事業用自動車向けのシステム開発の実証として、みちのりホールディングス、東京電力ホールディングス、関東自動車、福島交通、茨城交通らは、218台の電気バスを導入し、電気バス向けエネルギーマネジメントシステムバス(EMS)を開発しはじめています。みちのりがバスの運行管理最適化のノウハウ提供とシステムを、東電がエネルギー需給調整マネジメントシステムを担っています。
関西電力、大阪市高速電気軌道(大阪メトロ)、ダイヘン、大林組、東日本高速道路も、2022年度以降に、大阪メトロが電気バスを100台導入し、5社共同で運行管理や充電制御に関する実証実験を行って、2025年度の大阪・関西万博会場内外での電気バスの運行を目指しています。閉幕後も大阪市内で運行を継続し、2030年度まで実証実験を行います。
このようにエネルギーの地産地消とマネジメントの取組みが、個人単位のみならず、地区単位、カーシェアリング、事業用の車両でも大規模に実施されるようになってきています。
▷関連記事
・ソーラーカーポートの補助金制度とは?導入メリットも含めて徹底解説
・ソーラーカーポートとは?導入がおすすめな企業やメリット・デメリットを解説
・車の脱炭素化とは?日本の目標や矛盾点は?EVやハイブリッド車についても解説
▷グリラボSNSのフォローお願いします!!
Twitter @gurilabo
▷アイグリッドグループ