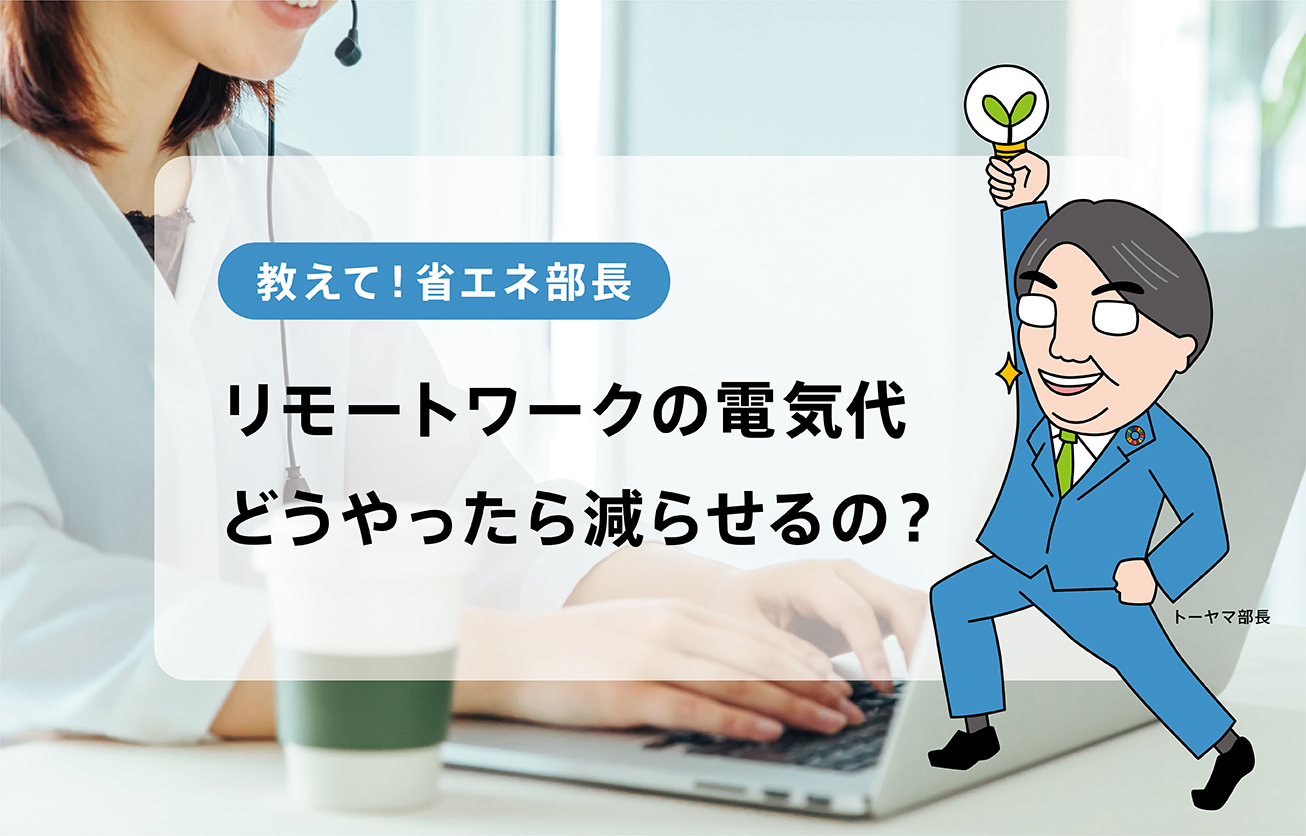とは?各ルールや今後の見通しについて解説.jpg)
出力抑制(出力制御)とは?各ルールや今後の見通しについて解説

2018年より九州電力で始まった出力抑制は、2022年以降、他の複数エリアでも実施されるようになりました。2024年には、東京電力でも出力制御を実施する調整に入ったといわれています。
本記事では、そもそも出力抑制とは何なのか、また何のために実施されるのかについて解説します。出力抑制を低減するための対策についても説明しているので、企業の電力管理担当になったばかりの方や、これから勉強したい方、興味のある方はぜひ参考にしてください。
出力抑制(出力制御)とは?
出力抑制(出力制御)とは、発電事業者が太陽光や風力などの発電所の出力を抑制することを指し、消費者へ電力を供給する役割を担う一般送配電事業者からの指示によって行われます。
出力抑制が行われるのは、発電量が需要に対して多すぎたときに、電力の需要と供給のバランスを取るためです。
しかし、出力抑制をしたところで発電事業者への補償はないため、発電事業者にとってはせっかく発電した再生可能エネルギーを捨てることになってしまいます。また、発電事業者が本来得られるはずの利益を得られなくなってしまうといった側面もあります。
出力抑制はなぜ必要?
出力抑制は、電力の需要量が供給量よりも少ないときに実施されます。消費と発電のバランスが崩れると、周波数や電圧に影響を及ぼし、最悪の場合停電になる可能性があるためです。
周波数が乱れると、送配電設備が故障したり、故障を防ぐために設備が自動停止したりする事態が発生します。機器が故障すれば、大規模な停電につながることも考えられます。
出力抑制は、実は太陽光発電や風力発電などの自然エネルギーのみで実施されているわけではなく、火力発電や水力発電も抑制の対象とされています。出力抑制を実施する順番は法令で決められており、5つの段階のうち、太陽光発電と風力発電は4番目に出力抑制が実施されることと決められているのが特徴です。
出力抑制には優先順位がある
日本における発電方法の中でも、太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーは、需要と供給のバランスを保つことが難しい電力です。そのため、出力抑制を実施する際には、発電コストや、発電を調整する技術のある電力から抑制を行うことが決められています。これを「優先供給」ルールと呼び、優先順位は以下の通りです。
①火力(石炭・石油・ガス)発電の調整、水力発電の揚水、蓄電池の活用
②他地域への送電など、地域間の連携
③バイオマス発電の調整
④太陽光発電と風力発電の抑制
⑤原子力発電・水力発電・地熱発電の調整
上記の通り、太陽光や風力によって発電された電力の出力抑制は、比較的低い順位で実施されます。また、原子力発電・水力発電・地熱発電といった、昼夜にかかわらず発電可能な「長期固定電源」と呼ばれる電力は、短期間で出力調整を行う技術を持ち合わせていないことから、最後に出力抑制される決まりとなっています。
出力抑制エリアは徐々に拡大している
出力抑制は、2018年度から2021年度までは九州電力のみで実施されていました。しかし、2022年以降、出力抑制の対象エリアは日本全国で広がってきています。2022年には北海道電力、東北電力、四国電力、中国電力など、出力抑制を実施する発電事業者が相次いでいます。
さらに、2023年に入ってからは中部電力、関西電力、沖縄電力も追加され、東京電力エリア以外のすべての電力会社が出力抑制を実施する運びとなりました。2024年には、東京電力でも出力制御を実施する調整に入ったといわれています。
太陽光発電所における出力抑制のルールと決まり方
次に、太陽光発電所が出力抑制を行う際の3つのルールを紹介します。なお、10kW未満の太陽光発電設備に関しては、2024年5月現在においては対象外となっているためご留意ください。
3つのルール
太陽光発電の出力抑制におけるルールは3つあります。それぞれの違いは以下の通りです。
旧ルール
旧ルールは、年間30日以内であれば、太陽光発電の出力抑制を無補償で要請できるルールです。新ルールが適用される前に決められたルールのため、旧ルールとされています。
新ルール
新ルールは、2015年のFIT制度改正によって取り入れられたもので、年間360時間を上限に出力抑制を実施できるものです。旧ルールでは1日単位で上限が決められていたため、1日のうちなら1時間であっても20時間であっても1カウントとしていました。
そのような旧ルールでは平等な運用がしにくいことから、時間単位の出力抑制ができるよう新ルールが設けられました。
無制限・無補償ルール
旧ルールや新ルールのように、出力抑制を実施する時間に上限を設けていないのが、無制限・無補償ルールです。無制限・無補償ルールは設定当初、国から指定された電気事業者のみを対象としていたため、「指定ルール」と呼ばれることもあります。
2021年には指定電気事業者制度が廃止されたため、どの電力会社の管轄でも無制限・無補償ルールが適用できるようになりました。
適用されるルールの決まり方
上記3つのルールのうち、どのルールが適用されるかは、発電エリアや接続契約を締結した時期によって異なります。どの電力会社にどのルールが適用されているのか、1つずつみていきましょう。
・北海道電力、九州電力
2015年1月25日まで旧ルール、2015年1月26日以降は無制限・無補償ルール
・東北電力
2014年9月30日まで旧ルール、2014年10月1日以降は無制限・無補償ルール
・東京電力、中部電力、関西電力、沖縄電力
2015年1月25日まで旧ルール、2015年1月26日から2021年3月31日まで新ルール、2021年4月1日以降は無制限・無補償ルール
・北陸電力
2015年1月25日まで旧ルール、2015年1月26日から2017年1月23日まで新ルール、2017年1月24日以降は無制限・無補償ルール
・中国電力
2015年1月25日まで旧ルール、2015年1月26日から2018年7月11日まで新ルール、2018年7月12日以降は無制限・無補償ルール
・四国電力
2014年12月2日まで旧ルール、2014年12月3日から2016年1月22日まで新ルール、2016年1月25日以降は無制限・無補償ルール
なお、これから10kW以上の太陽光発電を設置する場合は、条件にかかわらず無制限・無補償ルールが適用されます。
出力抑制を低減させるにはどうすればいい?
せっかく発電した再エネが無駄になってしまうだけでなく、発電所の利益も少なくなってしまう出力制限をできるだけ少なくするためにはどうしたら良いのでしょうか。考えられる2つの方法について解説します。
オンライン代理抑制を導入する
オンライン代理抑制とは、本来オフライン発電所が行うはずであった出力抑制を、オンライン発電所が代わりに行う方法です。
オフラインによる出力抑制は、発電所まで足を運び電源のオン・オフをしなければならないため、手間がかかります。そこで、すでにオンライン抑制に対応している発電事業者が、オフライン発電所の出力制御を代理で請け負うことで、スムーズな出力抑制の手助けをするのがオンライン代理抑制です。
オンライン発電所が代理で制御を行った分については、数カ月後にオフライン事業者からお金を受け取ることで、本来の出力抑制と同様の状態になるよう清算されます。オンライン出力抑制ではより柔軟な調整が可能となるため、制御量を少なくすることが期待できます。実際に、九州エリアではオンライン抑制によってすでに17%程度の低減に成功しています。
蓄電池を活用する
蓄電池を活用すれば、昼間に発電した電力を貯めておき、夜間に使うことが可能になります。近年では、出力抑制が発生した際に電力を蓄えられるよう、大型の蓄電池を設置している企業もあります。
蓄電池を活用して出力抑制を低減できれば、企業の利益が増えるだけでなく、クリーンエネルギーの効率的な活用にもつながり、脱炭素の促進にも有効です。
出力抑制にどう対応すればいいか悩んだら、アイ・グリッドへご相談を
出力抑制は、度重なる制度改正によってわかりづらい難点があります。また、今後は基本的に無制限・無補償ルールが適用されるため、出力抑制による企業の利益損失や、再生可能エネルギーの無駄が発生しやすいことも問題です。
せっかく発電した電力を無駄にしないよう、オンライン代理抑制や蓄電池などを活用し、少しでも有効に電力を使えるよう工夫することが重要です。アイ・グリッド・ソリューションズでは、出力制限への具体的な対応策に関するサポートも行っています。蓄電池の活用などを検討されている発電事業者の方は、ぜひ一度ご相談ください。
▷関連記事
・蓄電池や太陽光によるピークカット・ピークシフトとは?導入効果も解説
・FIP制度とFIT制度の違いとは?それぞれの概要もわかりやすく解説
▷アイ・グリッド・ソリューションズ関連はこちらをチェック