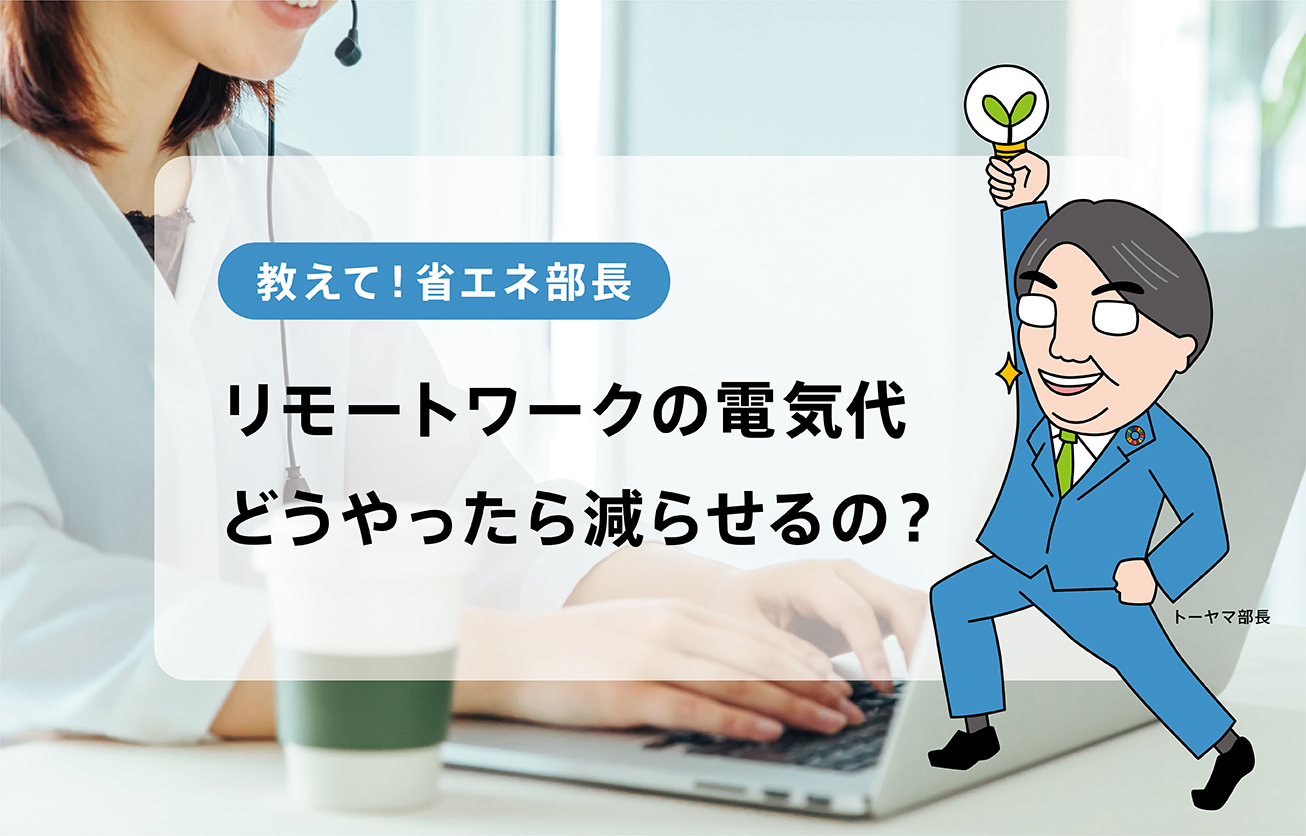【図解】太陽光発電の仕組みとは?メリット・デメリットもあわせて紹介
脱炭素化、持続可能な社会などに関連して、太陽光発電というキーワードを目にする機会が増えてきました。しかし、自社に導入を検討する前に、まず太陽光発電の基礎知識を全体的に知っておきたいという方も多いでしょう。
そこで本記事では太陽光発電の概要、仕組み、メリット・デメリット、導入・維持コスト、投資リスクや補助金制度、FIT終了後の運用などについて、網羅的に解説しています。CO2排出量やエネルギーコストの削減、BCP強化などの施策立案の参考にしてください。
太陽光発電とは?

太陽光発電とは、太陽の光エネルギーによって発電することです。日本では産業用だけでなく家庭用の太陽光発電システムも普及してきており、代表的な再生可能エネルギーとなっています。
では、現在日本で太陽光発電は、どの程度普及しているのでしょうか。一般社団法人 太陽光発電協会の「太陽光発電の状況」(2020年)によると、戸建て住宅総数に対する住宅用太陽光発電の普及率は9%でした。
FIT制度(※後述)の施行直後の2012~2014年では、年平均で約31万件と急速に普及が進みましたが、2019年は15万件と低調。以降2020年もコロナ禍の影響もあり、導入は激減しました。
しかし、大きな流れとしては、家庭から企業まで幅広い用途で活躍できる分散型電源として、太陽光発電の活用がさらに拡大することは間違いないでしょう。
太陽光発電の仕組み
太陽光発電は、太陽の光エネルギーを電気に変換する仕組みで発電しています。

上記のイラストをご覧ください。ソーラーパネルは幾つもの太陽電池で構成されており、太陽電池は「n型半導体」「p型半導体」という2つの板を張り合わせるように構成されています。
そして太陽光が当たると光エネルギーによって、「電子(-)」が「n型半導体」へ、「正孔(+)」が「p型半導体」のほうに集まります。この状態でそれぞれに導線を接続すれば電気を流すことができるのです。
ただし、これは現在主流になっているシリコン系太陽電池の原理です。以下のように複数の太陽電池がありますので、設置場所や用途に応じて選びましょう。
| 発電効率の目安 | 特徴 | |
| 結晶シリコン太陽電池 | 13~20% | 現在主流のタイプ。形状が豊富にある |
| 薄膜シリコン太陽光パネル | 7~10% | 薄型軽量タイプ |
| CIGS系太陽光パネル | 8~12% | 高温時の出力低下が少ない デザイン性が高いことでも人気 |
太陽光発電のメリット

太陽光発電システムの導入は企業にとって、以下の4つのメリットがあります。
- 環境保護
- エネルギー調達の安定化
- 売電収入、電気料金節約
- BCP強化
CO2を排出しないため、環境に優しい
太陽光発電は地球温暖化の原因となるCO2などの温室効果ガスが発生しません。このため、地球環境保護、脱炭素に貢献できます。
近年は社会的な責任を果たそうとする企業のなかで、太陽光発電システムの導入が進んできました。その背景には、気候変動等に関する持続可能な開発目標(SDGs)や温室効果ガス削減を掲げた「パリ協定」などの世界的な流れを受けて、2020年10月、菅首相が「2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指す」ことを掲げたことがあります。
企業は社会に認められてこそ存続を許されます。サステイナブル経営を実現するためには、自社が取り組める範囲で、太陽光発電などの再生可能エネルギーを導入することが欠かせません。
エネルギーが枯渇しない
太陽光発電は「再生可能」エネルギーと呼ばれるように、設備が劣化、故障しないかぎりエネルギーを作り続けられます。石油を燃やして電気に変える火力発電所のように、有限なエネルギー源を使うことがありません。
しかも、日本の気候では、ほとんどの場所で発電が可能です。従来、活用用途がなかった工場や倉庫、カーポートの屋根などを、無尽蔵のエネルギー創出場所に変えることもできるでしょう。
このような特徴は、エネルギー調達リスクを低くするためにも役立ちます。例えば、液化天然ガスの輸入価格の上昇や、新型コロナウイルスによる経済活動の停滞などによって、電気料金が高騰したのは記憶に新しいところです。自前で繰り返しエネルギーを得られる設備があれば、電力市場価格の変動による電気料金への影響を抑えられます。
収入を得られる
太陽光発電システムで発電した電気は、電力会社に売って収入を得られます。特にFIT(固定価格買取制度)の期間内は、買取価格が優遇されているため、初期費用を回収して収益化しやすくできるのです。
また、使用した分の電気料金は安くなり、コスト削減になります。さらに、電気購入の量が減ることで、一緒に徴収される「再エネ賦課金」(1kWあたり3.45円※2022年5月~)も削減できます。
工場や倉庫、大規模なオフィスビルなどでは、月々数百万以上の電気料金が発生することもめずらしくありません。このため、経費削減のために太陽光発電システムを導入する企業が増えています。
災害時に役に立つ
自然災害などによる停電時も、自立運転機能を持った太陽光発電システムなら、電気を使えます。自立運転機能とは、停電時に自家発電モードに切り替える機能で、今ではほとんどの太陽光発電設備に備わっています。
企業にとっては、太陽光発電導入はBCPの一環ともなるでしょう。実際、地域のライフラインを担っているスーパーでは、早期の営業再開を可能にするため、太陽光発電を導入する事例などが出てきました。
近年、異常気象による停電被害は増加傾向にあり、このような動きは、今後、物流センターや工場など、幅広い業種に拡大していく見通しです。
太陽光発電のデメリット
ここでは太陽光発電の主なデメリットとして、
- 発電量が天候に左右される
- 導入コストがかかる
- メンテナンス費用がかかる
の3つを解説します。
天候に左右される
太陽光発電は、天候や季節による日照量の変化に影響を受けます。そのため地域によっては太陽光発電システムの設置に適さないところもありますし、屋根の方角や角度などによっても発電量は変わります。
ただし、日照量が少ない日は電力会社から電気を購入すればよいため、発電できなくても極端に不便になることはありません。近年はソーラーパネルの性能も上がっており、日の出や日没近くでも発電できるようになっています。
いずれにしても、導入前には精度の高いシミュレーションをしておいたほうがよいでしょう。
導入コストがかかる
太陽光発電システムを導入するには、高額の費用がかかります。2021年の資源エネルギー庁の調査によれば、10kWのシステム費用の平均は25.0万円/kWでした。
kW数が増えるほど費用単価が下がる傾向にあるため、あくまで目安に過ぎませんが、住宅用、産業用の導入コストの概算を以下に示します。
| 住宅用(5kW) | 125万円 |
| 中規模産業用(100kW) | 2,500万円 |
| 大規模産業用(200kW) | 5,000万円 |
このように太陽光発電の導入には高額のコストがかかります。そのため、PPAモデルという初期費用ゼロ、メンテナンス費用ゼロで太陽光発電を導入できる仕組みも登場しています。
PPAモデルでは太陽光発電の電気を利用した分、PPA業者に電気料金を支払います。このため売電はできませんが、CO2排出量を抑えたり、価格変動リスクが低い再生可能エネルギーを調達できたりします。また、再エネ賦課金がかからないこともあり、一般の電力会社から電気を購入するより割安です。
メンテナンス費用がかかる
ソーラーパネル、パワーコンディショナなどの設備は経年劣化していくため、メンテナンス費用もかかります。点検とメンテナンスは法律で義務化されているため、出費を考慮しておきましょう。
こちらもあくまで目安ですが、費用相場を示します。
| 点検頻度 | 費用 | |
| 住宅用 産業用(50kW未満) | 4年に1回 | 1回あたり5~10万円 |
| 産業用(50kW以上) | 受変電設備:2ヶ月~6ヶ月に1回 パネル、パワーコンディショナ:6ヶ月に1回 | 年間100万円~200万円 |
点検の結果、修理や交換の必要があった場合は、さらに費用がかかることもあります。
太陽光発電導入の際に知っておきたいお金のこと

太陽光発電を導入するには膨大なお金がかかるのでは?という不安から、なかなか導入に踏み切れない企業も多いのではないでしょうか。ここでは、太陽光発電の導入で得られる経済的なメリットとして、太陽光発電投資、FIT制度、補助金制度の3つを紹介します。
低リスクで運用できる太陽光発電投資
太陽光発電投資とは、太陽光パネルで発電した電力を電力会社に売却して収益を得る投資方法のひとつです。太陽光システムは、一度設置すれば少ないメンテナンスコストで長期にわたって安定した収益が期待できます。
太陽光発電の表面利回りは10%前後と高利回りで、7〜10年程度で初期コストを回収できると言われています。ソーラーパネルの寿命が20〜30年程度であることを考えると、投資回収が済んでからも10年以上は継続的な収入を得ることが可能です。
また、太陽光発電は市場や経済状況などに左右されにくいことから、不動産や株式などと比較して低リスクな投資方法であるといえます。
太陽光発電投資を選んだ人からは、以下のような声が聞かれます。
・不動産投資に比べると初期コストが少ない
・SDGsに貢献しながら収益を見込める
・余っている土地を有効活用できる
新たな時代の投資先として、太陽光発電を検討する個人、企業が増えています。
コスト回収がしやすくなるFIT制度(固定価格買取制度)
FIT制度(固定価格買取制度)とは、太陽光発電などの再生可能エネルギーで発電した電気を、電力会社が一定価格、一定期間買い取ることを国が約束する制度です。
保証期間は発電量によって変わり、住宅向けは10年、法人・投資用は20年となっています。また、買取価格は設備費用の相場や、電力会社の電気料金などを加味して、一定の収益が見込める優遇された価格になるように設定されます。これによって、個人や企業はコスト回収の見通しを立てやすくなるわけです。
FIT制度が導入された背景には、
- 再生可能エネルギーを普及させる
- エネルギー自給率を高める
などがあります。
FIT制度の基礎知識を知りたい方は以下の記事をご覧ください。
導入時の費用負担を抑えられる補助金制度
FIT制度のほかにも、国や自治体は太陽光発電を普及させる補助金制度を整えています。
令和7年6月時点では「ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業」が行われています。概要は以下の通りです。
| 対象者 | 法人・個人事業主 |
| 目的 | 自家消費型太陽光発電や蓄電池などを導入する際の経費の一部を補助することで再エネ促進を加速化させ、2050年のカーボンニュートラルを実現すること |
| 補助対象 | 太陽光発電設備、定置用蓄電池、車載型蓄電池、充放電設備 |
| 補助額・補助率 | 4〜5万円/kW(太陽光発電設備)、3.9万円/kWh(業務・産業用の定置用蓄電池)、蓄電容量(kWh)× 1/2 × 4万円/kWh(車載型蓄電池)、機器費の2分の1+設置工事費1基あたり95万円(公共施設・災害拠点の充放電設備) |
なお、公募期間は令和7年6月5日〜令和7年7月4日(令和6年度補正予算二次公募・令和7年度予算一次公募)です。
国および各自治体の補助金情報を調べる際は、以下のリンクを利用すると便利です。
| 国の補助金 | 資源エネルギー庁「各種支援制度」 |
| 地方自治体の補助金 | Panasonic「全国の補助金がわかる」 |
太陽光発電に関するQ&A
ここでは太陽光発電の導入に関して、よくある質問を取り上げて回答します。
太陽光発電の設置費用はどれくらい?
2024年12月に発表された資源エネルギー庁の資料「太陽光発電について」によると、2024年度の10kW以上の事業用太陽光システムにかかる費用の平均値は22.6万円/kWでした。単純計算すれば、10kWなら226万円、100kWなら2,260万円の設置費用がかかる計算です。
詳しいシステム費用の内訳は、以下のとおりです。
| パネル | 8.6万円 |
| 工事費 | 7.5万円 |
| 架台 | 3.1万円 |
| パワコン | 2.7万円 |
| その他 | 1.6万円 |
| 設計費 | 0.2万円 |
| 値引き | -1.2万円 |
| 合計 | 22.6万円 |
太陽光パネルは設置するだけでなく、その後も定期的なメンテナンスを行う必要があります。資源エネルギー庁の同資料によると、2024年の太陽光パネルの運転維持費の平均は0.53万円/kW/年でした。単純計算すれば、10kWなら年間5.3万円、100kWなら年間53万円の維持費がかかることがわかります。
太陽光発電をやめた方がいいってほんと?
太陽光発電をやめたほうがよいとする主な意見は次のとおりです。
- FIT買取価格が下がっている(収益を出すまで時間がかかる)
- 日照量によって売電・自家消費量が変動しやすい
- 雨漏りが発生するリスクがある
- 反射光によって近隣トラブルになる
- 森林伐採して設置する場合は、CO2削減にならない
それぞれの意見にもっともな理由があるのは確かです。太陽光発電はある種の投資であるため、完全にリスクをなくしたい方にはおすすめできません。
しかし、売電収益やCO2排出量削減など目的がある方ならば、太陽光発電を導入するメリットはあります。信頼できる業者を選べば、多くのリスクやトラブルは未然に回避できます。
太陽光発電は10年後どうなる?
太陽光発電の導入から10kW未満は10年後、10kW以上は20年後にFIT制度の適応を受けられなくなります。いわゆる「卒FIT」となり、優遇された価格で売電できなくなるわけです。
しかし、卒FIT後も電力会社を選んで売電することは可能です。ただ、FIT制度よりも買取価格は安いため、自家消費量を増やして電気料金を抑えたほうがお得です。そのため、蓄電池を増設するなどして、自家消費量を増やそうとする個人、企業が増えています。
いずれにしても卒FIT後は、自分で小売電気事業者と買取契約を結ばないかぎり、余剰電力は一般送配電事業者が無償で引き受けてしまいます。企業の場合、事業者の手続きにある程度手間がかかるため、早めに準備しておくとよいでしょう。
まとめ
太陽光発電は再生可能エネルギーの代表格であり、国もFIT制度や補助金制度などによって普及を推進しています。導入側にはCO2排出量やエネルギーコストを軽減できる、災害時の非常電源として使える、などのメリットがあります。
一方、導入のハードルとなるのは高額な初期費用と、決して少なくない維持費です。株式会社アイ・グリッド・ソリューションズとVPP Japanでは、設備費用ゼロ、メンテナンス費用ゼロのPPAモデルによる太陽光発電システム導入サービスを提供しています。ぜひご検討ください。

▷関連記事
・PPAに適用される補助金はあるの?低コストで太陽光発電を導入する方法
・太陽光発電とはどんな発電システム?仕組みや歴史など基本情報を紹介!
▷グリラボSNSのフォローお願いします!!
Twitter @gurilabo
▷アイグリッドグループ