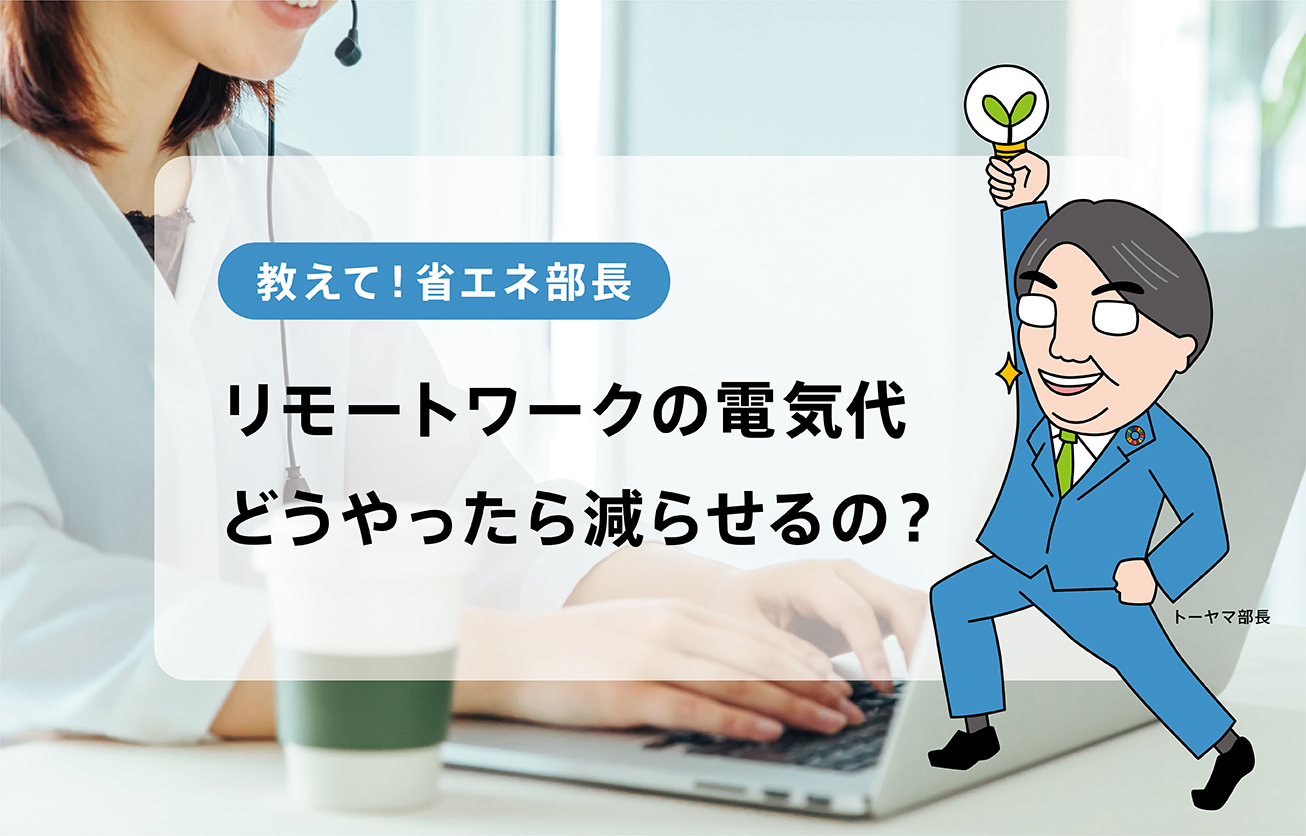GXの課題は?取り組み内容や方法を解説

日本では、2023年にGX推進法やGX脱炭素電源法が閣議決定されるなど、GXの実現に向けた本格的な取り組みを進めています。しかし、GX推進にあたっては多くの課題があり、まずは課題を解消することが脱炭素社会を実現するための第一歩です。
本記事では、国や企業におけるGX取り組みの課題や、GXが必要な理由、GXに関する法律などを解説します。環境問題に興味のある方や、そもそもGXとは何かを知りたい経営者や企業担当者はぜひ参考にしてください。
そもそもGXとは?
GXとは、グリーントランスフォーメーション(Green Transformation)の略で、「クリーンなエネルギーに転換すること」を指します。カーボンニュートラルを実現するにあたり、化石燃料からクリーンエネルギーへ転換することと、経済成長を両立させようという取り組みがGXです。
クリーンエネルギーとは、太陽光発電や風力発電、水力発電などの、発電時に二酸化炭素を排出しないまたは排出量を抑えたエネルギーのことです。
カーボンニュートラルを達成し、二酸化炭素の排出量を実質ゼロにするためには、多くの企業の協力が不可欠です。そこで、政府はカーボンニュートラル実現への取り組みを経済成長への機会と捉えることにより、産業競争力の向上も同時に実現しようとしています。また、GXを推進することは、エネルギーの安定供給にもつながると考えています。
GXが必要な理由
GXが必要な理由は、カーボンニュートラル達成の需要が高まっているためです。2020年、日本政府は2050年までにカーボンニュートラル達成を目指すと宣言をしました。カーボンニュートラルとは、二酸化炭素の排出量と吸収量を同じ量にすることで、二酸化炭素の発生を実質ゼロにするものです。
近年では、日本はもとより、世界中で地球温暖化によるさまざまな被害が発生しています。これ以上深刻な被害を出さないためにも、カーボンニュートラル達成は人類が早急に行うべき課題といえるでしょう。
国がカーボンニュートラルを実現するためには、二酸化炭素の排出量を減らす必要があり、企業や一般消費者の協力が不可欠です。 しかし、企業が二酸化炭素の排出削減に取り組むことで経済活動が制限されてしまうと、企業にとってカーボンニュートラルに取り組むメリットはなくなってしまうでしょう。
そこで、カーボンニュートラル達成に向け、あらゆる製品やサービスの省エネ化や脱炭素化を図ることにより、企業の経済活動を抑えることなく二酸化炭素排出量の削減を目指せる方法として、GXが推進されることになりました。
カーボンニュートラルを達成するためには、企業や国民が積極的に脱炭素に取り組めるような社会構造の転換が必要であり、GXはそのために必要な政策といえます。
GXにおける2つの法律
日本には、GXに関する法律が2つあります。それぞれ詳しく解説します。
GX推進法
GX推進法とは、脱炭素社会への円滑な移行を実現するための具体的な方針を示したものです。
先にも述べた通り、日本では2050年にカーボンニュートラル達成を公約しています。同時に、産業競争力や日本の経済成長を促すためには、2023年からの10年間で150兆円のGX投資が必要とされています。この150兆円のGX投資を進めることを目的として、GX推進法が制定されました。
GX推進法は主に5つの法定から成り立っています。概要を1つずつ解説します。
1.GX推進戦略の策定・実行
政府は、GXを総合的かつ計画的に推進するための戦略を策定する。策定した戦略は、GXへの移行状況を見ながら適切に見直す。
2.GX経済移行債の発行
政府は、2023年からの10年間でGX経済移行債(脱炭素成長型経済構造移行債)を発行する。GX経済移行債は、2050年までに化石燃料賦課金・特定事業者負担金によって返済する。
3.成長志向型カーボンプライシングの導入
二酸化炭素の排出量に値付けをすることで、GX製品や事業の付加価値を向上させる。先行投資支援と組み合わせ、GXに先行して取り組む事業者にインセンティブを付与する。
4.GX推進機構の設立
経済産業大臣の認可により、GX推進機構(脱炭素成長型経済構造移行推進機構)を設立する。
5.進捗評価と必要な見直し
GX投資の実施状況や国内外の経済動向等を踏まえ、施策の再検討や見直しを行う。化石燃料賦課金や排出量取引制度の制度設計について、排出枠取引制度の本格的な稼働に向けた方策等を検討し、GX法の施行から2年以内に必要な法律上の措置を行う。
参照:環境省
GX脱炭素電源法
GX脱炭素電源法とは、二酸化炭素を排出しない脱炭素電源の利用を推進しながら、電力の安定供給も図るための制度を整備する法律です。
日本においては、ロシアのウクライナ侵攻などによりエネルギーの価格が高騰し、今後エネルギー価格が下がる見通しも立っていない状況です。また、既存の火力発電所の老朽化や、原子力発電所が稼働していない状態が続くなど、電力の供給力が下がっていることも問題とされています。
上記に加え、GXへの取り組みによって、電力の安定供給とクリーンエネルギーの供給を両立する必要もあります。以上のことから、GX脱炭素電源法が定められました。
GX脱炭素電源法で定められている項目は「地域と共生した再生可能エネルギーの最大限の導入拡大支援」と「安全確保を大前提とした原子力の活用・廃炉の推進」の2つです。
「地域と共生した再生可能エネルギーの最大限の導入拡大支援」には、再生可能エネルギー普及のための具体的な支援策が盛り込まれています。一方で、「安全確保を大前提とした原子力の活用・廃炉の推進」には、原子力発電の安全対策や再稼働に向けた方針などが提示されています。
国のGXへの取り組みに対する課題は?
GXの実現に向け、国ではさまざまな取り組みが行われています。しかし、実際には課題が多く残っている状況です。
具体的には、国がGX経済移行債を発行して負担する、20兆円の返済財源をどうするかという点です。2023年からの10年で必要な投資額150兆円のうち、20兆円を政府が負担することになっています。しかし、GX経済移行債は国債の一種であるため、借金である以上返済しなくてはなりません。
返済にあてる財源の調達方法としては、炭素税の導入や、カーボンプライシングで発生した排出量取引の収入、電気料金に返済分を上乗せすることなどが考えられます。つまり、20兆円の借金を実際に負担するのは企業や国民であるため、負担が増えます。
また、GX経済移行債を発行しても、脱炭素市場が実際に活性化するかわからないことも問題です。企業がGXに取り組める環境を整えながら、脱炭素と経済成長を両立できる仕組みをいかに作っていくかが今後の課題となるでしょう。
企業にもGXは求められているが、同じく課題が多く残る
国だけでなく、企業においてもGXに関する課題は多くあります。特に、中小企業は大手企業に比べ、GXそのものへの関心や認知度が低いのが現状です。2023年に行われたフォーバルGDXリサーチ研究所の調査では、約8割の中小企業が「GXに取り組めていない」と回答しています。
中小企業にGXが浸透していない理由としては、GX実現に向けた国の方針が2022年に閣議決定されたばかりであるため、各企業の認識が追いついていないことが挙げられます。また、GXを推進するためには費用も時間もかかるうえ、効果が見えづらいという点も浸透しない理由のひとつでしょう。
人手や資金に余裕がない場合、短期的に利益が出にくいことへ積極的に取り組もうとする企業は少数派であるといえます。また、そもそも気候変動自体に無関心な経営者がいることも事実です。同調査では、気候変動についての情報を収集しない理由について「自社には関係ない」「自社にはまだ早い」と答えた企業が、約7割に及んでいます。
以上のことから、資金や知識、人材に乏しい傾向がある中小企業は、GXに取り組むことがなかなか難しいというのが現状といえます。
中小企業でも課題を払拭して着実にGXに取り組むには?
GXを実現するには、多くの企業が気候変動へのリスクを意識し、脱炭素に向けた積極的な取り組みを行うことが大切です。中小企業がGXへの課題を払拭し、取り組んでいくにはどうしたら良いのでしょうか。具体的な方法を3つ紹介します。
まずは脱炭素経営やGXについて知ることが大切
まずは、脱炭素の重要性を知ることが一番です。温室効果ガスを排出し続けることによる地球や人々への影響や、GXに取り組むことでどのようなメリットを得られるのか、中小企業が脱炭素に取り組むことの意味などを整理していきましょう。
特に、企業が脱炭素経営を行うことで得られるメリットを知ることで、GXに取り組むモチベーションの向上につながります。例えば、企業は脱炭素に取り組むことで以下のようなメリットを得られるでしょう。
・光熱費を削減できる
・認知度を向上させられる
・投資家から資金調達がしやすくなる
経営戦略として脱炭素を推進することで、自社のリスク軽減や成長につなげられることを理解することが重要です。
自社のCO2排出量を知り、長期的な視点でエネルギー転換への方針を立てる
次に、自社がどのくらいの二酸化炭素を排出しているかを測りましょう。そのうえで、まずは長期的な視点で脱炭素へ転換する方針を立てます。
自社の二酸化炭素排出量を知るためには、日本商工会議所の「CO2チェックシート」の活用が便利です。領収書を見ながら、電気代やガソリン代、灯油代とそれぞれの使用量を書き込むことで、自社の二酸化炭素排出量を知ることができます。
二酸化炭素排出量を把握したら、長期的な視点で脱炭素に転換していく方法を考えます。自社の事業の中で、少しでもクリーンエネルギーに切り替えられるものがないかを探りながら、段階的にエネルギー転換を進めていきましょう。
短期間でできるエネルギー削減活動から少しずつ取り組む
長期的なエネルギー転換の方針が決まったら、次に短期間で行えるエネルギーの削減計画を立てます。
例えば、使っていない部屋の照明を消す、空調機のフォルターを掃除して冷暖房効率を上げる、LED電球など省エネ設備を導入する、建物を部分的に断熱するなどが挙げられます。
簡単にできる省エネ方法は多くあるため、できることから取り組んでいきましょう。小さな取り組みが、新しい事業の発見につながることもあるかもしれません。
GXにどう取り組んでいくべきか悩んでいる企業はアイ・グリッドへご相談を
国では、2050年にカーボンニュートラルを実現するため、GXに関するさまざまな取り組みを行っています。しかし、GXにまつわる課題は多く残っており、脱炭素社会への妨げとなっている側面もあるのが現状です。
また、中小企業においてはGX自体の認識が進んでおらず、「自社には関係ない」と思っている経営者が多い事実もあります。中小企業は人材や資金に余裕がない場合も多いため、大がかりな取り組みは難しいかもしれません。また、何から始めればよいかわからない企業も多いでしょう。
アイ・グリッド・ソリューションズでは、企業の脱炭素経営への取り組みを支援しています。GXにお悩みの経営者や企業の担当者の方は、ぜひアイ・グリッド・ソリューションズまでご相談ください。この機会に、一緒に経営のチャンスを広げていきましょう。
▷関連記事
・GXとカーボンニュートラルの違いとは?それぞれの概要もわかりやすく解説
・なぜカーボンニュートラル人材の育成が必要なのか?脱炭素社会実現のための重要な視点とは
▷アイ・グリッド・ソリューションズ関連はこちらをチェック