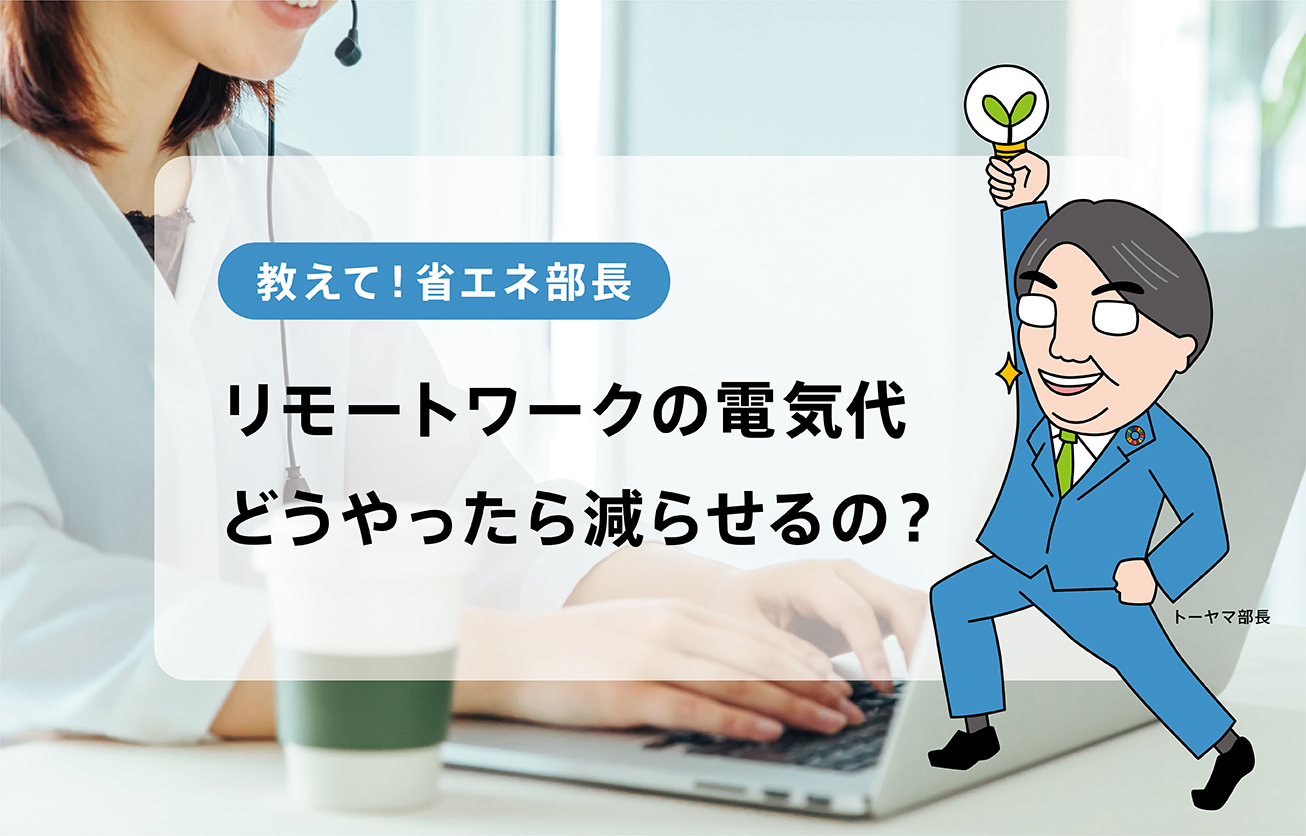分散型エネルギー源(DER)とは?メリット・デメリットについてわかりやすく解説
分散型エネルギー源(DER)という言葉をご存じですか?耳慣れない言葉かもしれませんが、太陽光発電、電気自動車などのように、一般住宅にもDERは存在しています。
この記事ではDERとは何か、メリット・デメリット、設備導入時に利用できる補助金、自治体のDERの取り組みなどについて解説しています。記事を読めばDERが意外に身近なものであること、自分もそれに参画できることが理解できるはずです。
分散型エネルギー源(DER)とは何か?

DERとは、需要家(電気などのエネルギーの利用者)が各地に分散して所有しているエネルギー源のことです。DERはDistributed Energy Resourcesの略で「分散型エネルギーリソース」とも言います。
DERの主な設備は、一般家庭や企業に設置された太陽光発電システムです。場所によっては、風力発電や地熱発電などの再エネもDERとして活用されているでしょう。
また、各地に分散してエネルギーをためられる設備もDERに含まれます。具体的には蓄電池、電気自動車、家庭用燃料電池(エネファーム)などです。
近年では電力会社とDERをつなげたVPP(バーチャルパワープラント、仮想発電所)も普及してきました。VPPでは電気が余っているときにDERの蓄電池にためておいたり、電気が足りないときに蓄電池の電気を送電したりできます。
つまり、地域全体を仮想的に1つの発電所のように連携することで、エネルギー利用を最適化するとともにリスクに強いシステムを構築できます。
分散型エネルギー源(DER)の意義
DERの意義は、エネルギーの「安定供給(Energy Securit)」、「経済効率性(Economic Efficiency)」「環境への適合(Environment)」を実現できることです。そして、これらの実現の前提として「安全性(Safety)」があります。
この意義はそれぞれの頭文字を取って「3E+S」と呼ばれており、国のエネルギー政策の基本にもなっています(下図参照)。
上図の内容を少しかみくだいて説明すれば、次のとおりです。
「安定供給」は地震や台風などの災害による停電が多い日本にとって、大きなメリットです。例えば停電時に自律的に発電できる太陽光発電システムや電気をたくわえた電気自動車があれば、リスクを減らせます。
「経済効率性」「環境への適合」はさまざまな要素がありますが、大きなところでは省エネ、CO2排出量削減です。これらが進めば、結果的に光熱費を減らせるメリットも出てくるでしょう。
「安全性」は全体の前提条件となる要素です。たとえ3Eを満たすにしても、各地に原発などの高リスクのエネルギー源をつくることは、多くの人が納得しないでしょう。
追加的な意義として、「地域活性化」「エネルギー供給への参画」「系統負荷の軽減」も掲げています。この取り組みの代表例は先ほど説明したVPPです。VPPがあれば電気の地産地消や、電力会社が余分な発電をしないことなどが実現できます。
分散型エネルギー源(DER)のメリット

ここでは、先に解説した3Eのメリットを、さらに具体的に次の3つに分けて解説します。
- 送電ロスを抑えられる
- 災害時に電気の供給が滞るリスクが減る
- 送電しにくい離島でも使える
DERによって身近な課題を解消できる場合もあります。
送電ロスを抑えられる
DERは消費地から近いところにあるため、送電ロスが少ないのがメリットです。一般的な集中型発電と違って、長距離の送電網が要らないため、送電ロスを大幅に減らせます。
日本の集中型発電の送電ロスは、設備にもよりますが3.4%ほどとされています。一方、旧式の発電所を持つ諸外国では、この数倍から数十倍の送電ロスが出ているケースもあるようです。
日本の送電ロス3.4%という数字はたいしたことではないと思うかもしれませんが、実は火力発電所7基ほどなくせるほどの電気量に相当します。しかし集中型発電の送電ロスを減らすのは技術的に困難であるため、DERによる送電ロスの削減が注目されています。
災害時に電気の供給が滞るリスクが減る
DERは消費地から近いところにあるため、災害時に電気の供給が滞るリスクが低いのもメリットです。外部電源なしに発電できる太陽光発電システムなどなら、地域全体が停電した場合でも電気を利用可能です。
資源エネルギー庁はDERの意義の1つである安定性について、”非常時のエネルギー供給の確保につながるなど、エネルギー供給リスクの分散化が可能”(※)と記載しています。近年は災害だけでなく、異常な暑さによる電力不足も発生しているため、自分の生活は自分で守るという姿勢が大切になっています。
送電しにくい離島でも使える
DERは送電線が引きにくく、送電コストもかかる離島でも使えます。このため離島は配電エリアの対象となりやすく、住民が不便を強いられるケースがありました。しかし、DERであれば、ある程度の電気量は自家発電できます。
このDERのメリットに注目した資源エネルギー庁は、電力ネットワークの次世代化の政策として、一般送配電事業者と配電事業者との連携を支援しています。今後、離島でのDER活用事例は増えていくでしょう。
分散型エネルギー源(DER)のデメリット
ここではDERのデメリットとして以下の2つを解説します。
- 導入コストが高い
- 再エネ発電では天候の影響を受ける
いずれも長期的にみれば大きな問題ではありませんが、DER導入時の検討項目になります。
導入コストが高い
DERは基本的に需要家(エネルギーを消費する側)の負担で設備を設置します。例えば太陽光発電パネルや蓄電池、パワーコンディショナーなどの初期費用がかかります。また、定期点検や修理などのランニングコストも発生するのもデメリットです。
ただし、後述するDER補助金を受けられれば、初期費用を抑えられます。また、自家消費による節約や売電収入などによってコスト回収するまでの期間を短くすることも可能です。
再エネ発電では天候の影響を受ける
太陽光発電や風力発電などの再エネ発電は天候の影響が大きいため、火力発電所や原子力発電所などに比べると安定的な供給ができません。このためDER単独での利用は難しく、地域の電力会社の利用と組み合わせます。また、蓄電池を設置して発電量が少ない場合に備える方法も一般的です。
再エネのDER導入を検討する際は、天候の影響をどれくらい受けるのか調べておくことも重要です。例えば太陽光発電の場合、設置場所の日照量から発電量をシミュレーションします。
DERの導入時に使える補助金
企業はDERを導入する際に使える補助金として、「再生可能エネルギー導入拡大に向けた分散型エネルギーリソース導入支援等事業費補助金(配電事業等の参入を見据えた地域独立系統の構築支援事業)」があります。
補助金の内容について、次の項で詳しく見ていきましょう。
再生可能エネルギー導入拡大に向けた分散型エネルギーリソース導入支援等事業費補助金
「再生可能エネルギー導入拡大に向けた分散型エネルギーリソース導入支援等事業費補助金」とは、蓄電池やエネルギーマネジメントシステムを導入する事業者に対し、事業に必要な経費の一部を補助するものです。再生可能エネルギーの導入促進や、電力需給を安定させることを目的としています。
補助金の公募は令和7年6月現在終了しており、すでに交付を受けている事業者に対する継続補助の募集が令和7年3月にも実施されました。現時点では新規事業者を公募する予定は発表されていないものの、令和8年以降に何らかの形で募集されることも考えられます。興味のある方は、資源エネルギー庁の公式サイトをチェックしてみてください。
参考として、令和7年度の募集内容を簡単に紹介します。
・対象事業者:以下の要件を満たす民間企業等
①日本に拠点を有していること。
②本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。
③本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。
④経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。
⑤経済産業省におけるEBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)に関する取組に協力すること。
⑥本補助事業により導入する補助対象設備の所有者であること。
⑦本補助事業により取得した補助対象設備を、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従い、当該マイクログリッドの運用のために必要な設備の活用を行う者であること。
⑧本補助事業により取得した補助対象設備の運用において法令、規程、その他各種セキュリティガイドライン等に基づいた適切な対策等を実施できる者であること。
⑨本補助事業により導入した設備の使用状況等についての報告を求めた際、それに対応できる者であること。
・対象設備:太陽光発電設備、風力発電設備、バイオマス発電設備、水力発電設備、地熱発電設備
・公募期間:令和7年3月3日~同年3月24日
・公式サイト:https://www.enecho.meti.go.jp/appli/public_offer/2024/0303_01.html
日本の分散型エネルギーシステムの構築に向けた取り組み例

資源エネルギー庁では、全国で大規模な分散型エネルギーシステムの実証を行ってきました。ここでは横浜市、豊田市、けいはんな学研都市(京都府)の事例を紹介します。
これらの実証事業では、以下の5つの成果が出ています。
| 成果 | 概略 |
| 1.CEMS等のエネルギーマネジメントシステムの開発 | 地域全体のエネルギー最適化のためのシステム(CEMS)を開発した |
| 2.ECHONET-Lite等の標準インターフェイスを確立 | 省エネ住宅用の通信仕様を確立できた |
| 3.蓄電池の統合制御システムの構築 | 蓄電池の遠隔操作などで電力需給を調整できた |
| 4.ディマンドリスポンスの効果検証 | 消費者がエネルギーを賢く利用できるようになった |
| 5.V2Hの実証 | EV車(電気自動車)、PHV車(プラグインハイブリッド車)のバッテリーを使って電気利用量を減らせた |
出典:分散型エネルギーシステムの構築に向けた取組|資源エネルギー庁
横浜市
横浜市では大型蓄電池を総合的に管理することで、市全体を仮想的な発電所と見立てる実証実験を行いました。参画した一般住宅は4,000戸、大規模ビルは10棟で、エネルギー最適化の成果が出ています。
出典:分散型エネルギーシステムの構築に向けた取組|資源エネルギー庁
豊田市
豊田市では太陽光発電や蓄電池、HEMSなどを導入した新築住宅67戸を対象に、エネルギーの地産地消の実証を行いました。具体的には、バーチャル パワー プラント(VPP)によって電力需給のバランス調整を遠隔操作で実施しています。
この結果、電力供給が余剰の際は各家庭の蓄電池に電気を貯蔵、逆に供給不足時には供給することで、地産地消比率を高められることが実証されました。また、需要家の節電(コスト縮減)にもつながったと言います。
出典:分散型エネルギーシステムの構築に向けた取組|資源エネルギー庁
けいはんな学研都市
けいはんな学研都市では住宅約700戸を対象に、VPPによる電力の需給バランス調整を実証しました。また、各家庭に電力会社による省エネコンサルを実施し、電力利用者が賢く電力使用量を制御する「ディマンドリスポンス」を向上できるか検証しました。
電力利用者側による省エネおよびCO2排出量削減は、2050年カーボンニュートラル達成のために不可欠です。けいはんな学研都市はスマート、スリムな未来都市のモデルとして、他の地域をリードすることを目指しています。
出典:分散型エネルギーシステムの構築に向けた取組|資源エネルギー庁
まとめ
分散型エネルギー源(DER)は、まだ耳慣れない言葉ですが、実は一般住宅の太陽光発電システムなどの身近なところで実現されています。DERの各設備をつないだVPP(仮想発電所)を構築する地域や都市も増えており、エネルギーの最適化が進んでいます。
グリラボは地球と社会と人の未来をつなぐことをテーマに、エネルギーの未来について研究し発信するメディアです。ビジネス、テクノロジー、カルチャーなど多様な領域をカバーしていますので、ぜひご覧ください。
▷関連記事
・【5分でわかる】自家消費型太陽光発電とは?メリットやデメリットについて紹介
・VPP(バーチャルパワープラント)って何?導入のメリットから事例までご紹介
・「地域連携BCP」とは?東日本大震災から10年。あなたの街を災害から守る
▷グリラボSNSのフォローお願いします!!
Twitter @gurilabo
▷アイグリッドグループ






 出典:
出典: