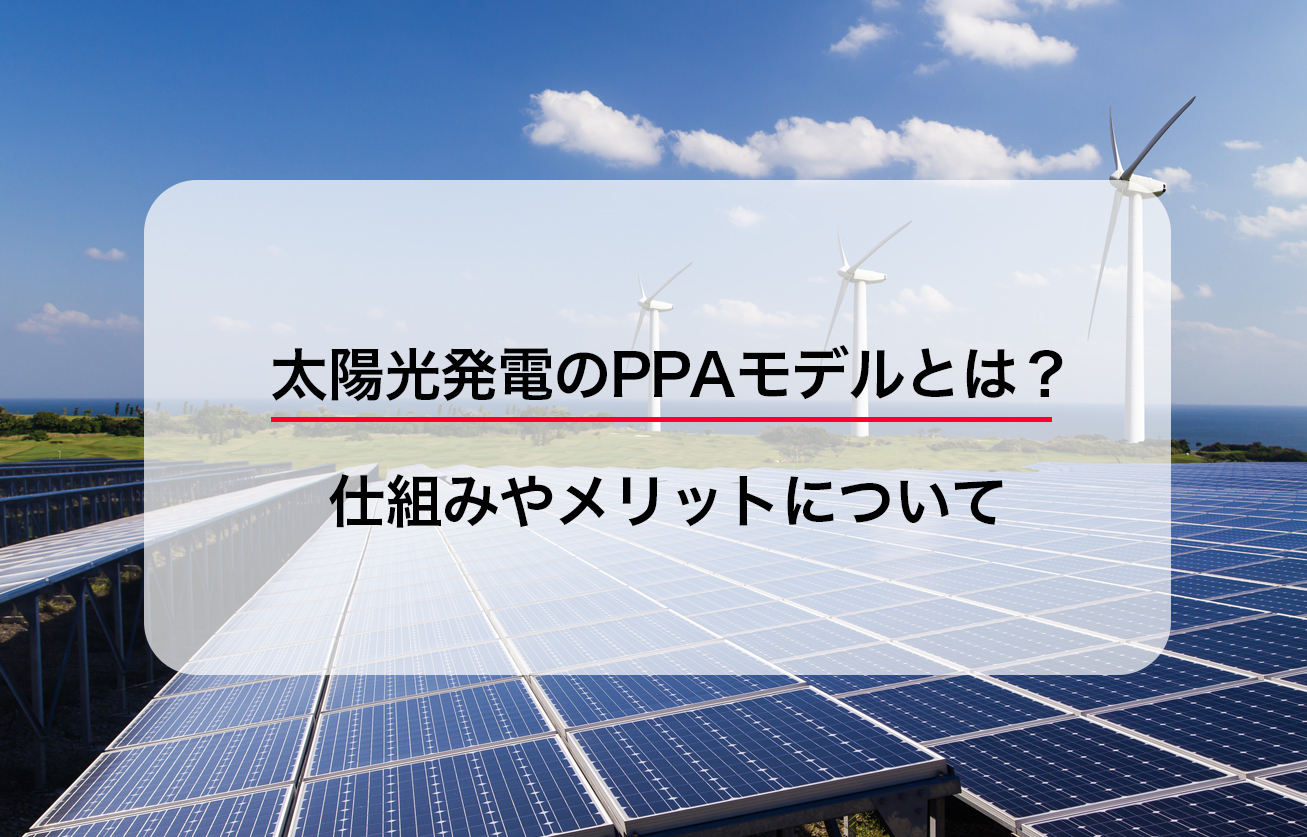
太陽光発電のPPAモデルとは?仕組みやメリットについて解説
PPAモデルとは初期費用とメンテナンス費用をかけずに、太陽光発電システムを導入できる仕組みです。今後ますます普及が予想されるPPAモデルに、興味を持っている人も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、PPAモデルの仕組みやメリット・デメリット、どのような企業に向く制度なのか、補助金制度は使えるかなどの基礎知識を解説します。一通りの知識を知っておけば、詳しい情報の収集や業者選びをスムーズに進められるでしょう。
PPAモデルとは、太陽光発電システムを導入する方法のひとつ

PPA(Power Purchase Agreement:電力販売契約)モデルとは、企業や自治体などが太陽光発電システムを導入する方法のひとつです。
PPAモデルは、 企業や自治体などの需要家が土地や屋根などの設置スペースを提供する代わりに、PPA事業者が初期費用やメンテナンス費用を全額負担するものです。発電された電力は、需要家である企業や団体が有償で購入する決まりとなっており、この契約をPPAと呼びます。
太陽光パネルを導入する場合、PPAの他に自己所有型やリースなどの選択肢もあります。3つの方法について、次の項で詳しく見ていきましょう。
| PPAモデル | 自己所有自家消費型 | リース | |
| 所有形態 | PPA事業者が所有 | 自社所有 | リース業者が所有 |
| 初期費用 | 不要 | 必要 | 不要 |
| 利用料 | 不要 | 不要 | 必要(リース料) |
| メンテナンス | PPA事業者 | 自社 | リース業者 |
| 余剰電力の売電収入 | なし | あり(FIT活用時) | あり(FIT活用時) |
| 自家消費分(※)の電気料金 | 有料 | 無料 | 無料 |
| 資産計上 | 不要 | 必要 | 必要 |
| 契約期間 | 10~15~20年間 | – | 10~15年間 |
※自家消費:太陽光発電で創った電気を施設内で使うこと
太陽光発電システムを導入する方法は主に3つ
企業や自治体が太陽光パネルを導入する際、3つの選択肢から選ぶことが可能です。以下に、それぞれの概要や特徴を解説します。
PPAモデル
PPAモデルは「第三者所有モデル」とも呼ばれ、PPA事業者が需要家の敷地や建物のスペースに、太陽光発電設備を無償で設置・維持管理して電気を供給する仕組みです。
PPAモデルの特徴は以下のとおりです。
| メリット |
・設備導入とメンテナンスの費用をかけずに太陽光発電設備を導入できる ・太陽光発電の電気を使うことで、電気代を節約できる ・CO2排出量を減らすことで、企業のイメージアップや投資を呼び込む効果を期待できる |
| デメリット |
・契約期間が通常10~15~20年間と長い ・気候条件や設置条件によっては、導入ができないことがある。契約を断られることがある |
上記のメリット・デメリットについては、後ほど詳しく解説します。
PPAモデルにおいて需要家が設置コストを負担しなくて良い理由として、PPA事業者と需要家が「電力販売契約(PPA)」を結ぶことが挙げられます。「電力販売契約(PPA)」は、PPA事業者が発電した電力を需要家が購入するという契約で、PPA事業者は電気代で利益を出せることから、Win-Winの関係が築けるのです。
もちろん、設置した太陽光発電で電力をまかなえなかった場合は、従来どおり電力会社から購入することも可能です。
自己所有型
自己所有型は、自社で太陽光発電システムを導入して、維持管理していく方法です。当然ながら多額の初期費用がかかり、メンテナンス費用も負担しなければなりません。
自己所有型の特徴は以下のとおりです。
| メリット |
・長期間順調に稼働すると、他の方法より投資効率が高くなる ・余剰電力を売って収入を得られる |
| デメリット |
・設備導入とメンテナンスの費用負担が大きい ・資産計上するので財務指標に影響が出て手続きが面倒 |
従来は売電収入を目的として、太陽光発電システムを自社設置する企業がほとんどでした。しかし、現在は買い取り価格が下がってきているため、利益を出しにくくなりました。PPAモデルが人気になっている背景には、このような事情もあります。
リース
リースはリース事業者から太陽光発電システムを借りる方法です。基本的にはリース料にメンテナンス費用も含まれているので、故障や交換が発生しても追加費用は発生しません。
リースの特徴は以下のとおりです。
| メリット |
・設備導入とメンテナンスの費用をかけずに、太陽光発電設備を導入できる ・余剰電力を売って収入を得られる(FIT活用時) |
| デメリット |
・月々のリース料が発生する ・リース資産として計上しなければならない ・契約を終了すると何も残らない |
リースはPPAモデルと似ていますが、あくまで設備をレンタルし、その費用を支払っているところが違います。したがって、太陽光発電システムで創った電気は無料で利用でき、売電も可能です。
PPAモデルのメリット

PPAモデルを活用すれば、費用や手間をかけずに再生可能エネルギーを調達できます。さらに、環境保護に積極的に取り組むことで、企業が間接的に得られるメリットもあります。
初期費用を抑えられる
先に説明してきたように、PPAモデルでは基本的に初期費用がかかりません。そのため、資金に余裕がなくても、高額の産業用の太陽光発電システムを導入できます。また、銀行から融資を受けるための手続きも要りません。
さらに、PPAモデルでは通常、資産計上されませんので、事業の財務諸表から切り離せます。つまり、経理・会計処理の手間を増やすことなく、再生可能エネルギーを調達できます。
電気代の負担を減らせる
太陽光発電システムで創った電気は、再エネ賦課金がかからないため割安です。再エネ賦課金とは、簡単にいえば、再エネ利用を増やすために国民全体が負担している税金のようなものです。具体的には、再生可能エネルギーで発電した電気を買い取るFIT制度を維持する財源に使われています。
再エネ賦課金は年度によって、以下のように変動しています。
| 2019年5月分~2020年4月分 | 2.95円/kWh(税込) |
| 2020年5月分~2021年4月分 | 2.98円/kWh(税込) |
| 2021年5月分~2022年4月分 | 3.36円/kWh(税込) |
※低圧供給・高圧供給・特別高圧供給
PPAモデルはすでに再エネ普及に貢献しているため、この再エネ賦課金を請求されません。一方、電力会社から電気を購入すれば、上記の分を余計に支払うことになります。
実際のところ、企業はいくらぐらいのコストカットが見込まれるのでしょうか。仮に、基本料金単価が1,200円/kW(税別)のとき、30施設で200kWの太陽光発電設備を導入した場合、年間約3,000万円のコストカットが見込めます。初期費用もメンテナンス費用と手間もかからないことを考えれば、十分な投資効果といえるでしょう。
メンテナンスは再エネ会社にお任せ
太陽光発電の所有者はPPA事業者ですから、メンテナンス、修理もすべて任せられます。発電量が下がればPPA事業者の収入も減ってしまうため、スピーディーに対応してもらえるでしょう。
例えば、太陽光パネルが劣化したり故障したりしても、無償で業者が交換してくれるため、別途資金を準備しておく必要はありません。電力系統に接続するために必要な設備も同じように対処してもらえます。PPAモデルは15~20年間の長期解約になるため、メンテナンス費用と修理、故障などによる追加費用がかからないのは安心です。
CO2排出量の削減になる
再生可能エネルギーの1つである太陽光発電を導入すれば、CO2排出量を削減して環境負荷を減らせます。これによって、クリーンな企業へのステップアップにできるケースもあるでしょう。例えば、太陽光発電の電気を利用するEV充電サービスを提供することで、顧客満足度を高める企業などが増えてきました。
近年では、再エネ100%で事業活動することを目指す国際的な運動「RE100」に加盟する企業も増えています。審査を受けて「RE100」に加盟できると、環境保護や社会問題解決に取り組む企業が選ばれる「ESG投資」を呼び込みやすくなる面もあるからです。
PPAモデルのデメリット
PPAモデルは長期契約なので、慎重に検討する必要があります。また、設置場所によっては契約を断られる場合もあります。
長期契約が必要
PPAモデルは、PPA事業者によっても異なりますが、一般的に10~15年の長期契約を結びます。20年契約の場合もめずらしくありません。
長期契約によるデメリットを具体的に挙げると以下のとおりです。
自家消費型よりも月々の節約額が少ない
PPAモデルは低リスクな投資ですが、その一方、月々の節約額は自家消費型より少なくなります。契約期間中は売電による収入もありません。
自社都合で太陽光発電システムを移動、廃棄すると違約金が発生する
設備はPPA事業者の所有物なので、事業所の移転、転売などの際に、勝手に移動や撤去ができないことに注意が必要です。また、建物が老朽化している場合も、リフォームや建て替えの可能性があるため、PPAモデルを利用しにくい面があります。
設置場所に制約がある
設置場所や発電容量の条件によっては、PPA事業者の利益が期待できないため、契約を断られることがあります。具体的には以下のようなケースです。
・日照量が不十分な地域
・積雪や塩害、強風などへの特別な対策が必要な場合
・適切な設置場所を確保できない場合(スペースや屋根の向き、角度など)
・設置容量が少なすぎる場合
・設置工事やメンテナンスの負担が大きい場合
審査基準はPPA事業者によって違うため、不明な点がある場合は相談してみましょう。なお、上記のほかにも、企業の信頼性や経営状態なども審査されます。
PPAモデルに関する疑問Q&A
ここでは、PPAモデルに関してよくある質問にQ&A方式で回答します。
PPAモデルの事業者一覧を知りたい
PPA事業者の公的な事業者一覧データはありません。
例えば、登録小売電気事業者は資源エネルギー庁が取りまとめていますが、PPA事業者にはこのような事業者一覧はありません。そこで、以下に主な事業者の情報をまとめましたので、参考にしてください。
| 事業者 | 特徴 | 公式サイト |
| アイ・グリッド・ソリューションズ | ・蓄電池、EV充電池を含めた災害停電に強い太陽光発電システムを導入できる ・1施設あたり年間108万円のコストカットの実績 |
https://www.igrid.co.jp/ |
| 関西電力 | ・地域電力会社として関西電力を利用している企業は利用しやすい | https://sol.kepco.jp/taiyoko/ |
| Looopでんき | ・Looopでんきの電気プランに加入すると電気代が割引になる ・送配電費用が発生する点に注意 |
https://looop.co.jp/service/prosume |
| エクソル | ・設置企業の条件に最適なPPA事業者をマッチングしてもらえる | https://www.xsol.co.jp/industry/self_consumption/4/ |
| オリックス | ・蓄電池を含めた太陽光発電システムを導入できる | https://www.orix.co.jp/grp/business/corporate_ppa.html |
PPAモデルはどんな施設におすすめ?
以下のような施設におすすめです。
・再エネ電力を安く導入したい場合
・初期投資が準備できない、しにくい場合
・維持管理や撤去など、設置後の作業を行いたくない場合
・新築、築浅など長期利用を想定できる施設
PPAモデルは初期費用がなくメンテナンスの手間と費用もかかりません。ただし、長期契約になるため、安定して太陽光発電を続けられるかどうかも検討しましょう。
PPAモデル導入に関する補助金はある?
PPAモデルを導入する際に活用できる国の補助金として、「ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業」を利用できます。
この補助金は、自家消費型の太陽光パネルや蓄電池を導入する企業などに対し経費を一部補助することで、太陽光パネルの導入を促進をするものです。
PPAモデルだけなく自己所有型やリースの場合でも適用されますが、ここではPPAモデルのケースで概要を簡単に紹介します。
・対象団体:民間企業、個人事業者(青色申告)、学校法人、一般社団法人など
・対象設備:太陽光発電設備、定置用蓄電池、車載型蓄電池、充放電設備(※蓄電池・車載型蓄電池どちらかの導入が必須)
・補助金:5万円/kW(太陽光発電設備)、3.9万円/kWh(業務・産業用の定置用蓄電池)、蓄電容量(kWh)× 1/2 × 4万円/kWh(車載型蓄電池)、機器費の2分の1+設置工事費1基あたり95万円(公共施設・災害拠点の充放電設備)
・公募期間:令和7年6月5日~同年7月4日 正午(令和 6 年度補正予算の二次公募・令和 7 年度予算の一次公募)
・公式サイト:https://www.eic.or.jp/eic/topics/2025/st_r06c/1st/
詳細な情報は、上記の環境イノベーション情報機構公式サイトより確認してください。
まとめ
PPAモデルは初期費用やメンテナンス費用をかけずに太陽光発電システムを導入できることから、普及が進んでいます。メンテナンスもPPA事業者が実施してくれるため、追加費用もかかりません。
また、再生エネルギー利用促進のために、国からの補助金も出ています。コストカットや地球環境への貢献など、自社の目的に応じてPPAモデルの活用を検討してはいかがでしょうか。
▷関連記事
・PPAに適用される補助金はあるの?低コストで太陽光発電を導入する方法
・太陽光発電にかかる費用は?太陽光導入の知識や流れを徹底解説
▷グリラボSNSのフォローお願いします!!
Twitter @gurilabo
▷アイグリッドグループ











とは何か簡単に解説。実践例もあわせて紹介-1.jpg)




