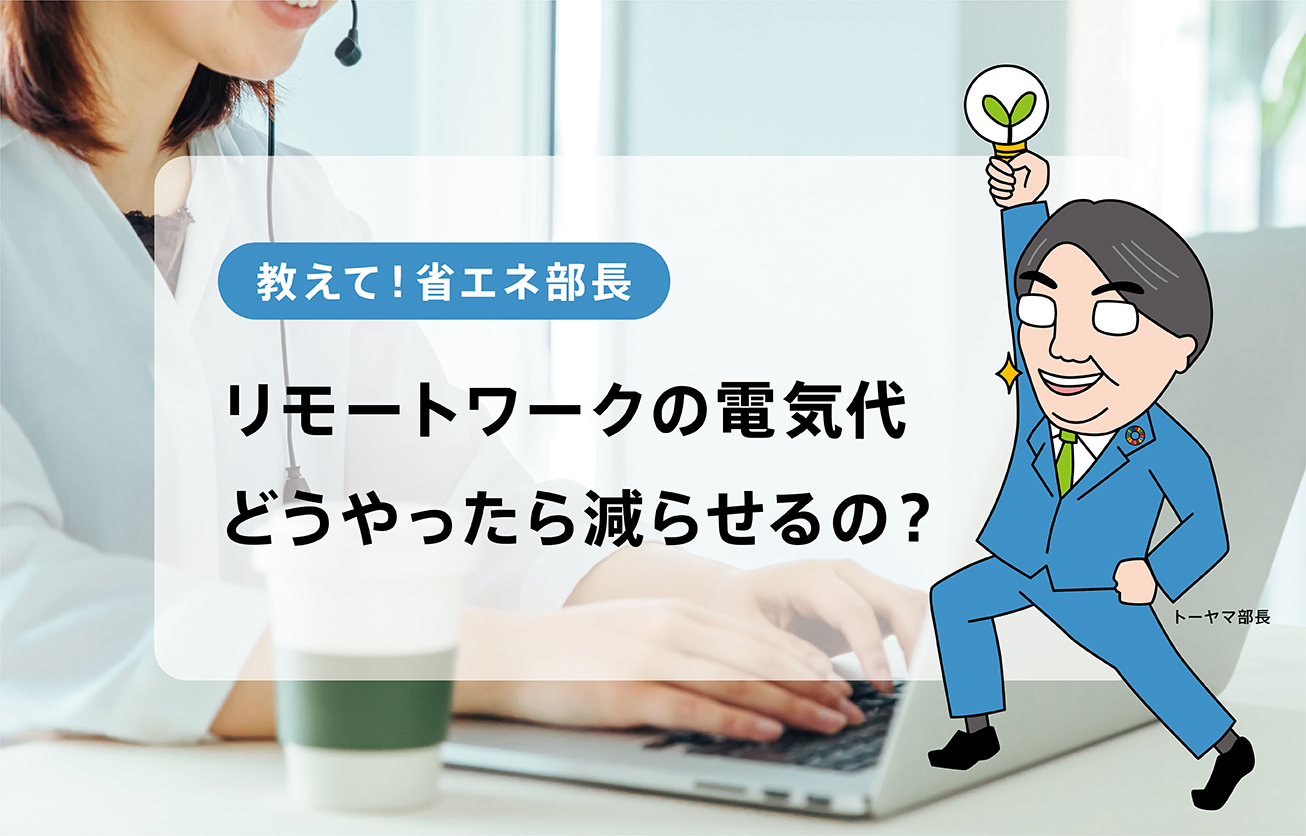物流の2024年問題って何?問題点や影響をわかりやすく解説

2024年問題とは、物流業界の時間外労働が短縮されることによって生じる、さまざまな変化や課題の総称です。物流業界に携わる人だけでなく、一般の消費者や荷主にも大きく影響を及ぼすため、物流・運送業界にかかわる企業には早めの対応が求められています。
本記事では、物流の2024年問題の内容や法律上の変更点、企業が取り組むべき対策などを解説します。今後どのような対策が必要なのかを知りたい物流・運輸業界の人は、ぜひ参考にしてください。
物流の2024年問題とは?
2024年問題とは、2024年4月1日から施行される働き方改革関連法案によって、トラックドライバーの時間外労働が規制されることで生じる諸々の問題を指します。
物流業界は業務の特性上、長時間労働になりやすいことが課題の1つとして広く認識されています。働き方改革関連法案で時間外労働の規制が厳しくなると、これまでと同じ量の荷物を運べなくなってしまい、さまざまな側面で問題が生じるでしょう。
例えば、物流業者の売上減少やドライバーの収入減少、荷主や一般消費者の運賃負担の増加やサービスの質の低下などが懸念されています。物流業界の経営者や従事者は、問題が大きくなる前に早めの対策を行うことが必要です。
働き方改革関連法案による時間外労働の規制は、大企業では2019年4月に、中小企業では2020年4月にすでに始まっています。物流業界や建設業界、医療業界においては5年間の猶予が設けられていましたが、2024年4月に猶予期間が終わり、どの企業も適用されることが予定されています。
物流の2024年問題と関連する働き方改革の主な変更点
働き方改革関連法の適用によって、物流業界が大きく影響を受けると予想されるのは、主に以下の4つです。
1つめは、時間外労働と休日労働の上限規制です。今までトラックドライバーの自動車運転業務において時間外労働の規定はなかったものの、2024年4月からは時間外労働の上限が設けられます。上限は原則月45時間・年360時間ですが、物流業界では36協定の特別条項を定めた場合に限り、年960時間まで時間外労働の許可を得ることができます。
2つめは、時間外労働が月60時間を超えた場合の割増賃金率引き上げです。これまでは時間外労働における賃金割増率は原則25%以上、大企業では50%以上でしたが、2024年4月からは企業の規模に関わらず割増賃金率50%以上に変更されます。
3つめは、勤務間インターバル制度の導入です。勤務間インターバル制度とは、就業から次の始業までにインターバルを9時間以上設けることを義務とし、11時間以上設けることを努力義務とするものです。
4つめは、正規雇用と非正規雇用との待遇差を解消する同一労働・同一賃金の適用です。これは、正規と非正規社員とで給与・賞与に差をつけないことや、非正規社員から待遇の差について説明を求められた際、企業側に説明責任があるとした決まりです。
その他、拘束時間の制限や連続運転時間の規制などの変更点もあり、物流業者は対策に迫られています。
物流の2024年問題に何も対策しないとどうなる?
2024年4月に働き方改革の関連法が適用される物流業界で、何も対策を行わなかった場合はどうなるのでしょうか。考えられる影響を3つの立場から解説します。
物流業者が受ける影響
トラックドライバーの労働時間が減少すると、単純に運べる荷物の量が減少します。これまでと同じ輸送能力を維持できなければ、対応できる業務が減り、企業の売上や利益の減少につながるでしょう。
これまで通りの業務量を維持するには、トラックドライバーの増員が必要です。しかし、時間外労働の規制によってドライバーの収入が減少するとなると、離職の増加や採用活動の難航など、人手が集まりにくい状況になることも考えられます。また、時間外労働の割増賃金率も上がるため、人手不足であるにもかかわらず人件費は増加するという悪循環にもなりかねません。
荷主が受ける影響
物流業界では、人件費の高騰や利益減少により運賃の値上げが発生すると予測されるため、荷主が販売する商品の価格や送料にも影響を与えます。
物流業者の人手不足により配送を断られたり、翌日配送に対応してもらえなくなったりするなど、消費者が求めるサービスに対応できなくなる可能性もあるでしょう。食品や冷蔵品など、素早く届ける必要のある商品はとくに影響が大きくなることが懸念されます。そのほか、長距離の輸送を依頼できなくなったり、事務の手間が増えたりするといった影響も考えられます。
一般消費者が受ける影響
物流業界が人手不足になることで、一般消費者はこれまで可能だった当日・翌日配送サービスを受けられなくなる可能性があります。配達までの日数がかかると、野菜や果物、水産物などの生鮮品を受け取ることも難しくなるでしょう。
また、運賃が値上がりすると、一般の消費者が負担する配送料も高くなります。当日・翌日配送サービスには追加料金が必要だったり、再配達時に追加料金がかかったりするなど、これまでよりも送料の負担が大きくなることが懸念されます。
2024年問題に向けて物流業界が取り組むべき課題

2024年問題に対応するため、物流業者は取り組むべき課題と対策をしっかり把握しておく必要があります。企業ができる対策として、以下に3つの方法を紹介します。
1.人材の確保
人手不足によるサービスの量と質の低下を防ぐため、早めに人材を確保しておきましょう。時間外労働が減少すればその分運べる荷物の量が減り、企業にとっては売上や利益の減少につながります。
一方で、時間外労働が減少することでトラックドライバーの収入減が見込まれ、離職率が高まる可能性もあります。今働いているドライバーの労働環境や待遇を見直し、これまで以上に働きやすい環境を作っておくことも大切です。また、女性や高齢者も活躍できる労働環境であると、より人材を確保しやすくなるでしょう。
2.荷主や一般消費者の理解促進
物流の2024年問題は、物流業者だけで完結する問題ではないため、荷主や一般消費者にも配送コストの増加やサービス内容の変化について知っておいてもらう必要があります。できるだけ早期に広報の強化を行い、周知しておきましょう。
例えば、自社のHPやブログ、SNS、パンフレットやチラシなどの紙媒体を通して、問題を理解してもらうことが有効です。荷主や一般消費者にあらかじめ知らせておくことで、配送料の値上げをスムーズに行えるとともに、自社の事業を守ることにもつながります。
3.システム導入によるDX化の推進
労働時間が減少してもこれまでと同じ量の荷物を運ぶには、システムを導入してDX化を推進し、業務効率化をはかることが必要不可欠です。システム導入によって業務の一部がDX化できれば、無駄な労働時間が減り、効率的な配送につなげられるでしょう。
例えば、物流業界の課題のひとつに、荷待ち時間が長い点が挙げられます。トラック予約受付システムを活用すれば、荷待ち時間を削減してトラックの稼働率を上げることが可能です。また、AIを活用して業種の異なる荷主をマッチングさせ、共同輸送を実現している企業もあります。
別の方法として、在庫管理システムで在庫の過剰や不足をなくし、作業の無駄を省くことも有効です。
業務効率化を実現し、残業時間が少ない企業であることをアピールできれば、多くの人材が集まることも期待できます。
物流業界はDX化が必須。ただしDX化による影響にも対策が必要
物流の2024年問題は、物流業界だけでなく、消費者や荷主にも大きな影響を与えます。今後の影響を把握するとともに、自社の業務効率化を図り、サービスを維持できるよう努めなければなりません。積極的にシステムを導入し、コストや手間を削減しましょう。
ただし、システム導入でDX化を図ることは、新たなコストがかかることを意味します。利益を維持するために、システム選びは慎重に行う必要があるでしょう。また、DX化が進めば進むほど、電力コストや災害時の影響などが心配な一面もあります。デジタルに依存するリスクを把握し、トラブル時も事業を継続できる計画を立てておくことが大切です。
災害時に必要な電力を確保するためには、アイ・グリッド・ソリューションズが提供する「GX Logistics」の活用もおすすめです。GX Logisticsは、物流センターに太陽光発電システムや大型蓄電池、EV充電サービスなどを統合的に設置するサービスです。災害に強く環境に優しいシステムで、どのような状況においても事業をスムーズに行える企業体制の構築を実現します。
▷関連記事
・【インタビュー】全国に拠点を持つ企業ならではの物流センター屋根を活用した 具体的な取り組みは?
・【インタビュー】スポーツをもっと⾝近に。⾃然と共に過ごす企業ならではの取り組みは?
・経済省の「GX実現に向けた基本方針」の概要|企業が押さえておきたい知識とは?
▷グリラボSNSのフォローお願いします!!
Twitter @gurilabo
▷アイグリッドグループ