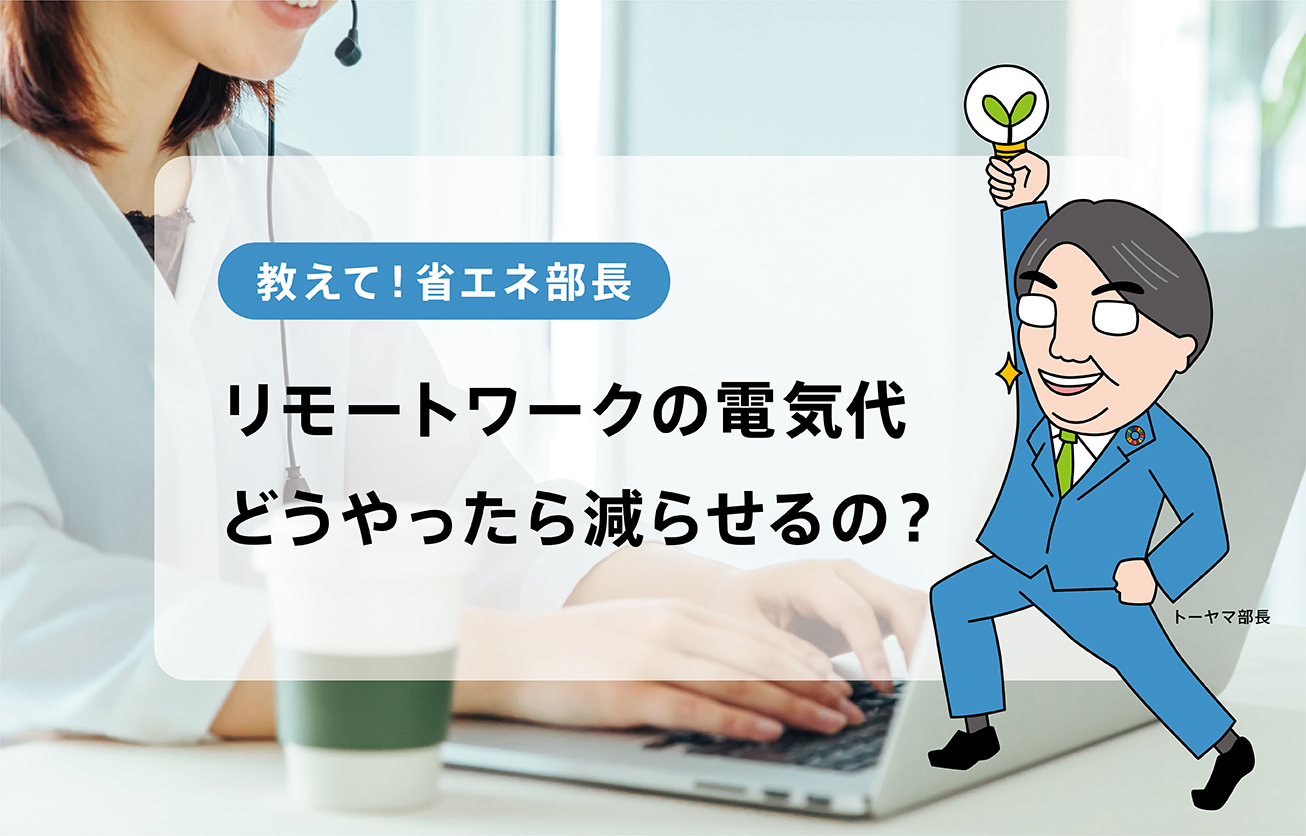COP27エジプト現地視察 ~気候変動に対する世界と日本のギャップが浮き彫りに~【現地視察レポート】
2022年11月7日(月)から11月20日(日)までCOP27がエジプトのシャルム・エル・シェイクで開催されました。グリラボを運営している株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ代表取締役社長の秋田智一はJCLP(日本気候リーダーズ・パートナーシップ)視察団の一員として、現地を訪れました。本記事は、COP27を現地視察した秋田による考察をまとめています。記事を読むことで、世界と日本の気候変動に対する様々なギャップを知ることができるので、世界の気候変動に対する最新の動きを知りたい方はぜひ参考にしてください。
COP27とは?

COPとは国連気候変動枠組み条約締約国会議(Conference of Parties)の略称です。今回で27回目の開催となるため「COP27」と呼ばれています。国連加盟国が気候変動対策に関して定期的に打合せをするために、1995年の開始以降ほぼ毎年開催されており、日本でも1997年12月に京都でCOP3が開催されました。
COP27では下記の内容が決定されました。
・「シャルム・エル・シェイク実施計画」の採択
科学的知見と行動の緊急性、野心的な気候変動対策の強化と実施などについて、COP26全体決定「グラスゴー気候合意」の内容を踏襲しつつ、緩和、適応、ロス&ダメージ、気候基金などの分野で、締約国の気候変動対策の内容強化を求める内容となっています。
・「緩和作業計画」の採択
緩和とは、温室効果ガスの排出量削減と吸収の対策を行うことです。緩和作業計画は2030年までの緩和の野心と実施を緊急に高めるために策定されました。1.5℃目標達成の重要性や計画期間を2026年までとして毎年議題として取り上げて進捗を確認すること等が盛り込まれています。
・ロス&ダメージ基金(仮称)と移行委員会の設置
ロス&ダメージとは気候変動の悪影響に伴う損失と被害のことです。特に途上国の多い南半球で発生しやすく、これまで先進国と途上国との間で意見の隔たりがありました。COP27は議論された結果、脆弱な国へ支援するために資金面での措置を講じること、その一環としてロス&ダメージ基金(仮称)を設置すること、運用化に関してCOP28に向けて勧告を作成するため移行委員会を設置することが決定しました。
参考:環境省|国連気候変動枠組条約第27回締約国会議(COP27)、京都議定書第17回締約国会合(CMP17)及びパリ協定第4回締約国会合(CMA4)の結果について
JCLP(日本気候リーダーズ・パートナーシップ, Japan Climate Leaders’ Partnership)とは?

JCLPは持続可能な脱炭素社会の実現には産業界が健全な危機感を持ち、積極的な行動を開始すべきだという認識のもと発足した、日本独自の企業グループです。
アイ・グリッド・ソリューションズは2022年5月にJCLPの加盟企業となり、その一環として視察が実現しました。
参考:持続可能な脱炭素社会の実現を目指す企業グループ「日本気候リーダーズ・パートナーシップ(JCLP)へ加盟
アイ・グリッド・ソリューションズ代表取締役社長 秋田による重要キーワード4つを紹介

秋田がCOP27の視察を通じた考察を4つに絞ってご紹介いたします。日本と世界での気候変動に対する温度感や認識の違いに着目してご覧ください。
① ロス&ダメージ(気候変動の悪影響に伴う損失と被害)
COP27でキーワードのひとつとして感じたのは、“ロス&ダメージ”です。ロス&ダメージとは、気候変動の悪影響による短期的損失と中長期的被害を意味します。気候変動による災害や干ばつなどの被害は、経済や生活の基盤が脆弱な発展途上国で起きやすいです。そのため途上国の方々にとって気候変動は経済・生活・人命に直結するものであり、既にアフリカ各国ではGDPの5~15%が毎年失われているとみられています。途上国における1人当たりのCO2排出量は先進国と比べ1/6~1/7であるにも関わらず、気候変動による影響を大きく受けているのは途上国であることから、道徳的な憤りも強く感じられます。
ロス&ダメージは当初交渉議題には入っていませんでしたが、今回COPがアフリカ大陸で初開催であったこともあり、途上国側の強い姿勢によって主要議題となりました。結果として、気候変動による被害を支援するため、途上国を対象に新たな基金「ロス&ダメージ基金(仮称)」を創設することが決まりました。この基金は途上国にとって画期的だと言える点が2点あります。
1点目は気候変動によって被害を受けたとき賠償されることです。現状途上国ではレジリエンスや保険といった賠償制度が存在していません。基金の設立によって、賠償制度の運用が可能となるかもしれません。
2点目は、ロス&ダメージ基金が先進国の歴史的な排出量に対する賠償として機能することです。これまで先進国を中心に排出されてきた温室効果ガスの累計は、既に途上国への被害という形で繋がっています。したがって先進国の過去の温室効果ガスの排出を賠償していく仕組みが成立したという観点においても、アフリカのCOPは偉業だったと言われています。
来年以降はより各国の立場や対応が具体的になっていくでしょう。気候変動の影響を直に受け、身近に感じているのは発展途上国の方々ですから、彼らの再エネを推進していこうという姿勢は変わらないと思います。
再エネ推進の動きとして、インドは石炭火力の段階的な削減という目標から石油・LNGを含めた化石燃料の段階的な削減を提起するようになりました。これは化石燃料に頼るよりも再エネを自分たちで作ったほうが、圧倒的にコストが削減できることを認識しており、転換を図っているためです。再エネと経済はトレードオフではなく両立可能なトレードオンの関係にあり、排出量を削減しながら経済成長は可能であることを表しています。欧州もロシアの資源はないものと考え、再エネシフトを加速するという国が大勢を占めており、日本で起きている石炭回帰の議論はほとんどされていませんでした。
② 日本の「環境政策」と世界の「産業政策」
日本では脱炭素の問題やCOPは環境政策で語られますが、海外では産業政策として語られており、企業間、各国間の競争として捉えられています。COP27に関しても、海外では官房長官・経済産業大臣クラスの方が出席されており、日本のように総理大臣や経済産業大臣が参加していない国は少ないです。この観点からも日本は気候変動問題を産業政策だと認識しておらず、環境政策として捉えていることを示唆しているのではないでしょうか。
日本はここ2~3年で大きく欧州に後れを取っているように見えます。欧州では再エネ自体が経済的なメリットを発揮していることもあり、出来るかどうかではなく、誰がやるかというステージに入っています。日本では脱炭素化が可能か否かという議論が行われていますが、海外では実行段階がすでに出来上がっており、誰がやるか・誰が先頭に立つのかという争いになっています。欧州に加えて、インフレ抑制法案により米国も46兆円規模の予算を組んで、脱炭素を中心とした成長戦略を描いています。この予算を消化しきれば脱炭素は実現できるということをしきりに言っており、各企業はイニシアチブ(主導権)の取り合いになっているのが現状です。産業政策としての脱炭素に対するゲームルール(合理的意思決定の構造)は既にできてしまったように思います。
③ 日本の報道の問題点 – 気候変動と健康問題の紐づけ

■写真:ジャパン・パビリオンにてJCLPのパネルディスカッション
日本の報道では「地球温暖化」という言葉が使われていますが、世界では「Global Warming」と言う人はおらず、「Climate Change」や「Climate Crisis」と表現しています。我々のような環境問題に取り組む企業で地球温暖化という言葉を使っていると、恥ずかしさすら感じます。
報道という観点では、情報・報道の関連づけについて課題があるように思います。
海外の研究調査は気候変動による影響をあらゆる機関(NGO・NPO等)によって関連付けています。例えば、大気汚染やPM2.5が喘息を引き起こしたり、気候変動が生活に影響しストレスを増大させることでメンタルヘルスに悪影響を与えたりすることなどが報告されています。データ量も多く、日本の厚労省が持っていないような日本のデータも持っていたりするほどです。
このような研究調査によれば、気候変動は遠い国のシロクマの話ではなく、身近な健康問題に及んでいます。医師免許を持っている海外の活動家たちが、喘息をどう治療するかではなく、上流の要因にある気候変動問題を解決しなければ根本的な解決にならないと、言っているほどです。
海外の報道では、気候変動問題が干ばつや熱波にも影響していることが当たり前のように関連付けられていますが、日本では異常気象は異常気象、気候変動問題は気候変動問題で単独に報道されており、関連付けられていません。気候変動に対する報道が各国と比べて少ないわけではないのに関わらず、自分たちの身近な事象と紐づけられていないことにより、気候変動問題に対するAwareness(気付き・認識)にずれが生じてしまっています。
Awarenessを作っていくことによって、政府などに対するロビーイングにもつなげることもできます。これは民間企業にもできることです。リーダーシップは政府だけのものではないと、医学雑誌ランセットの方が言っていたのが非常に印象的でした。各国の研究調査結果がこれだけ揃ってきているような状況では、海外と同じような流れは必ず日本にもやってきます。つまり、データやエビデンス、ニュースが気候変動と異常気象を関連付けて語られるようになってくれば、気候変動に対する世論も整ってくるのではないかと感じます。
④ 日本と世界の目標設定の在り方の違い

■写真:ニューヨークタイムズ主催のパネルディスカッション
日本の企業の方と話していると、経済的範囲内でできることをコツコツとやりますという方が多いように思います。つまり、ゴールから逆算するのではなく積み上げでやっていこうという考え方です。
海外は、先に目標を立てバックキャスティングで進める考え方が主流です。今ない技術を含めてゴールを設定することで、イノベーションが起き、ビジネスチャンスへと繋がると捉えられています。一方、日本ではいまある技術での課題解決を考える傾向にあります。そのためバックキャスティングで目標を設定すると、「達成できない目標を掲げてどうするんだ」という考えの方が多くなります。海外の一見出来なさそうな目標を掲げ、イノベーションで解決していくという考え方に対して日本は非常に否定的。
COP27に参加されていた世界の海運大手会社の責任者は、
「海運という非常に難しいところで脱炭素ゼロという目標を掲げた時に、最初はどうやって実行するかという答えはなかった。今ない技術を自分たちでどう作っていくかというところにビジネスチャンスがあって、他より早くやることで、脱炭素の文脈において、競争優位を築ける。自分たちが先に行動を起こすことで、価格競争から、環境価値にゲームチェンジできる。コストだけで見られていた世界から全く違う世界へと変えることができる」
と言っていたのが印象的でした。やれることだけをやっていては、現状の技術から発展もないしチャンスもないと誰もが言います。
日本で言えば、環境政策はやらなければならないことであり、その中にビジネスチャンスはないと思ってしまっています。コストでしかないから、極力小さく遅くやろうという考え方です。
海外は、「グリーンに行くのは未来であり、自分たちが先にやればチャンス」という考え方をしています。従来とは異なるゲームルールに参加できなければふるい落とされてしまうという脅威となり、早く大胆にやらないと意味がありません。変革に失敗はつきものなので、ロスリーダーになっても勇気と意思を持って脱炭素を推進しています。
デンマークの電力会社オーステッドの代表Mads Nipper氏は「痛みは長くは続かない。結果、収益も倍、収益率も倍増以上」と言っています。2008年に石炭85%、再エネ15%だった電源構成を2040年までに再エネ85%、石炭15%の比率に逆転させる計画を立てイノベーションを起こしていった結果、たった10年でやってしまいました。いまや日本の電力10社を足しあげた時価総額よりも高い時価総額となりました。
2008年の状況を考えると、日本ではFITもまだ始まっていない状況で、当時はかなりリスクの高い状況だったと思います。
まとめ
今回はアイ・グリッド・ソリューションズ代表の秋田がCOP27に視察へ行き、現状や考察を以下の4つに絞ってご紹介いたしました。
① ロス&ダメージが大きい発展途上国を対象に新たな基金を創設するとともに、再エネシフトの動きはますます加速するだろう
② 日本では気候変動対策は環境政策として語られるが世界では産業政策として語られている
③ 日本の報道では気候変動が他の現象と関連付けて報道される機会が少ない
④ 日本はいまある技術をもとに目標を設定し課題解決を行うことに対し、世界ではまだ存在しない技術を含めた目標設定を行い、バックキャスティングでイノベーションを起こしながら課題解決を行う
気候変動問題は世界共通の課題です。この記事を読んで、気候変動や世界の脱炭素に関する動きを考える機会となれば幸いです。
グリラボはエネルギーの世界をわかりやすく紹介しているメディアです。脱炭素やESGの知識を深めたい人はぜひ参考にしてみてください。
▷関連記事
・気候変動とは?原因や対策、現状の深刻な影響を分かりやすく解説
・地球温暖化の影響とは?現在身近で起きていることや日本の状況を解説
▷グリラボSNSのフォローお願いします!!
Twitter @gurilabo
▷アイグリッドグループ