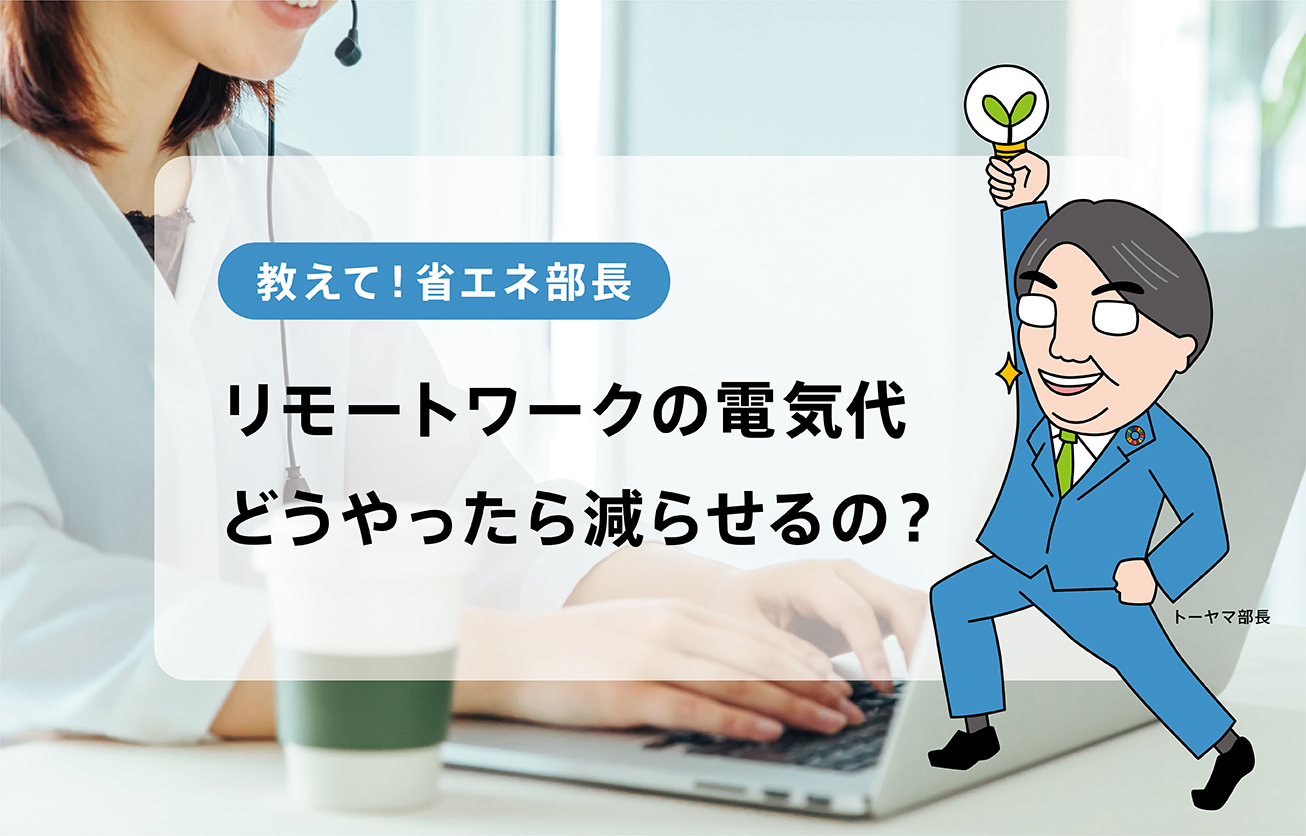【図解あり】脱炭素とは何か?どこよりもわかりやすく簡単に解説!
地球温暖化による気候変動が懸念される中で、「脱炭素」という言葉を耳にする機会が増えてきました。ニュースでよく目にするけれど、何を指す言葉なのかよくわからないという人もいるかもしれませんね。
この記事では、脱炭素とは一体何のことなのか、簡単にわかりやすく説明していきます。
脱炭素とは温室効果ガスの実質ゼロを目指すこと
脱炭素とは、地球温暖化の原因となる代表的な温室効果ガスである二酸化炭素の排出量をゼロにしようという取り組みのことです。また、二酸化炭素排出が実質ゼロになった社会のことを「脱炭素社会」といいます。地球温暖化の加速を受けて、世界全体で脱炭素に向けた取り組みが推進されています。
日本においては、2020年10月に、当時の菅義偉内閣総理大臣が「2050年までに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわち2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指す」と、所信表明演説の中で述べました。
これを受けて、環境省では「2050年までに年間で12億トンを超える温室効果ガスの排出を実質ゼロにすること」を目標として、産業構造や経済社会の変革に取り組んでいます。ここでいう「実質ゼロにする」というのは、後述する「カーボンニュートラル」の概念のことを指しています。
なぜ世界は脱炭素を目指しているのか?
どうして、今世界中で脱炭素に向けた取り組みが推進されているのでしょうか。大きな理由として、次の2点が挙げられます。
地球温暖化による気候変動
18世紀の産業革命以降、石炭や石油などの化石燃料を大量に燃やすようになったことで、人類の二酸化炭素排出量は急激に増加しました。二酸化炭素は地表の熱が宇宙に逃げることを妨げる「温室効果」という働きを持っています。そのため、大気中の二酸化炭素が増えることで、地球温暖化が加速しているものと考えられています。
地球の温度が上昇すると、海面上昇や酸性化、洪水や干ばつなど、自然環境や私たちの生活にも大きな影響をもたらすといわれています。地球温暖化の対策を講じることは、人類の急務ともいえるのです。
化石燃料の資源がなくなるため
人類が経済活動に使用しているエネルギー資源は、石炭、石油のほか、天然ガス、原子力発電の燃料であるウランといったものがあります。私たちの生活に欠かせないこれらの化石資源ですが、実は、近い将来に枯渇すると予測されているのです。2019年時点で、石油と天然ガスは50年、ウランは115年、石炭は132年が寿命と考えられています。
このことから、化石燃料に代わるエネルギー資源の確保が急がれています。
関連記事:脱炭素はなぜ必要?知っておきたい世界共通の目標と成り立ち

脱炭素社会を知る上で知っておきたい言葉
脱炭素社会について語るうえで、知っておくべき3つの言葉をご紹介します。
| パリ協定 | 世界の平均気温を産業革命以降に比べて2℃より低く保つことを目標とした協定。 |
| SDGs | 「Sustainable Development Goals」の略語。国連加盟国の全会一致で採択された、持続可能でよりよい社会を目指すための国際目標。 |
| カーボンニュートラル | 二酸化炭素の排出量と吸収量を均衡させて、排出全体を実質ゼロにすること。 |
脱炭素に関する知識を深めるにあたり、必ず目にする言葉といっても過言ではありません。それでは、これらの言葉について詳しく解説していきます。
関連記事:脱炭素はなぜ必要?知っておきたい世界共通の目標と成り立ち
パリ協定
パリ協定とは、2015年にパリで開催されたCOP21(第21回気候変動枠組条約締約国会議)で合意し、2016年に採択された協定です。「世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く保ち、1.5℃に抑える努力をする」という目的のもと、加盟国への二酸化炭素排出量の削減目標策定や実施状況の提出を促します。
アメリカ、中国、EU、インド、日本といった温室効果ガス排出量上位国を中心に、多数の国や地域が加盟しています。
SDGs
SDGs(エス・ディー・ジーズ)とは、「Sustainable Development Goals」の略語で、2015年9月の国連サミットにおいて加盟国197ヵ国の全会一致で採択された、持続可能でよりよい社会を目指すための国際目標です。
全部で17の大きな目標が掲げられており、2030年までに達成することを目指しています。
1.貧困をなくそう
2.飢餓をゼロに
3.すべての人に健康と福祉を
4.質の高い教育をみんなに
5.ジェンダー平等を実現しよう
6.安全な水とトイレを世界中に
7.エネルギーをみんなに そしてクリーンに
8.働きがいも経済成長も
9.産業と技術革新の基盤を作ろう
10.人や国の不平等をなくそう
11.住み続けられるまりづくり
12.つくる責任 つかう責任
13.気候変動に具体的な対策を
14.海の豊かさを守ろう
15.陸の豊かさも守ろう
16.平和と公平をすべての人に
17.パートシップで目標を達成しよう
これらの目標の下には、さらに196の具体的なターゲットが設定されています。
「⑦エネルギーをみんなに そしてクリーンに」の中では再生エネルギーの割合を拡大させること、「⑬気候変動に具体的な対策を」では気候変動に対する適応や対策などが挙げられており、脱炭素とも大きく関連のある取り組みです。
カーボンニュートラル
カーボンニュートラルとは、二酸化炭素の排出量と吸収量を均衡させて、排出全体を実質ゼロにすることです。経済活動や日常生活による二酸化炭素の排出を削減するだけでなく、森林管理などによって吸収量を増加することで、合計ゼロの状態を目指します。
パリ協定においても、平均気温の目標設定とともに「今世紀後半に温室効果ガスの人為的な発生源による排出量と、吸収源による除去量との間の均衡を達成すること」が盛り込まれており、脱炭素社会における重要な概念といえます。
脱炭素の社会をつくるために世界が取り組んでいること4つ

脱炭素社会を実現するため、具体的にはどのような取り組みが行なわれているのでしょうか。世界の代表的な取り組みを、できるだけわかりやすく解説します。
再生可能エネルギーの活用
再生可能エネルギーとは、量に限りがある化石燃料と違い、比較的短期間で再生でき、枯渇せず何度も使うことができるエネルギーのことです。水力・風力・地熱による発電、森林の間伐材や家畜の排泄物などのバイオマス燃料を利用するバイオマス発電やバイオマス熱利用が再生可能エネルギーにあたります。
再生可能エネルギーは、石炭や石油のように発電時に大量の二酸化炭素を排出しないという特徴を持っています。
世界でエネルギーを作り出すために排出される二酸化炭素の量は、1990年の約210億トンから、2018年には約332億トンと、増加の一途をたどっています。脱炭素社会を目指すにあたって、エネルギー起源の二酸化炭素排出量を削減することは必須であり、世界中で再生可能エネルギーの導入が推進されています。
日本においては、エネルギー資源の8割近くを石油や石炭といった化石燃料が占めているのが現状です。さらに、エネルギー資源の調達についてもほとんどを輸入に頼っており、エネルギー自給率は6%と他の主要国に比べても低い数値となっています。
二酸化炭素排出量の削減とエネルギー資源の確保という観点から、再生可能エネルギーの活用は日本においても重要な課題といえるでしょう。
水素エネルギーの発展
水素を燃焼させると、電気と水が発生します。この電気をエネルギー源として生活に使用するのが水素エネルギーの試みです。発電時に二酸化炭素を排出しないため、脱炭素社会において化石燃料にかわる主力エネルギー源になるのではないかと期待されています。
水素は、水に代表されるように、化合物として様々な物体の中に存在しています。例えば、水に電圧をかけて電気分解することでも、水素を取り出すことができます。水のほかにも様々な物質から簡単に取り出すことができ、その水素を貯蔵しておくことも可能です。エネルギー源として使い勝手がいいところも、注目を集める理由となっています。
水素エネルギーは、すでに実用化が進められている技術です。例えば、ガスに含まれる水素と空気中の酸素を使って発電ができる家庭用燃料電池や、燃料電池を動力とするバスなどが普及しています。
飛行機や車の脱炭素化
自動車や飛行機といった乗り物でも大量の化石燃料が利用され、二酸化炭素排出の大きな要因となっています。脱炭素社会の実現にあたっては、電気自動車の一般普及や再生可能エネルギー燃料を動力とする飛行機の導入も、避けられない課題となるでしょう。
日本における電気自動車の普及率は2020年時点で新車販売台数のうち0.6%と、まだまだ石油エンジンが主流であることが伺えます。しかし、世界では電気自動車への転換は確実に進んでおり、2040年までには半数にのぼると予想されています。
また、日本航空では、廃プラスチックや使用済みの食用油を燃料とする航空機の導入を進めており、2050年には二酸化炭素排出を実質ゼロにする方針を固めています。
太陽光発電でエネルギーを自家発電
太陽光発電は、シリコン半導体などに太陽光が当たると発電する現象を利用した発電方法です。一般住宅でもよく目にするようになった太陽光パネルには、シリコン半導体を使った太陽光電池が内蔵されています。
太陽光発電は、二酸化炭素を排出しない再生可能エネルギーのひとつです。また、屋根や空き地などの余剰スペースを活用して発電することができるというメリットもあります。電力会社の設備とは独立して家庭や企業での自家発電が可能になるため、非常用電源としても注目されています。
近年では、小中学校に太陽光パネルを設置する動きも出ています。横浜市では、2024年の春までに65校で導入を進める方針を打ち出しており、これによって二酸化炭素排出量を従来よりも2割削減できるそうです。
脱炭素のために個人が今からできること
国をあげた社会的な取り組み以外にも、個人が取り組めることはあるのでしょうか。脱炭素社会に向けて、私たちができる活動を紹介します。
再エネ電気を供給している電力会社と契約する
再生可能エネルギーを利用した電力を供給している電力会社と契約しなおすことも、脱炭素につながります。
2016年に電力の小売りが全面自由化されて以降、大手電力会社だけでなく、一般企業も電力販売に乗り出すようになりました。その中には、再生可能エネルギーによる電力のみを供給する「再エネ電気100%」を掲げる企業もあります。
例えば、アイ・グリッド・ソリューションズが提供しているサービス「スマ電CO2ゼロ」では、二酸化炭素排出量がゼロのエネルギーを供給しています。毎月の電気代も従来の電力と同等に収まるよう工夫されており、個人でも利用しやすい方法です。
プラスチック製品の購入・利用を減らす
海洋プラスチック問題をきっかけに、世界で脱プラスチックの動きが広まっていますが、脱炭素の観点からもプラスチック削減は重要です。
プラスチックは石油を原料としているため、焼却すれば二酸化炭素を排出します。日本のプラスチックごみの半数以上が焼却処分されているため、二酸化炭素排出量が増加する一因になっているといえます。
レジ袋の有料化にともない、日本でもエコバッグを持つ人が増加しました。ほかにも、マイボトルを持ち歩いたり、紙ストローを使用したりすることもプラスチックの削減になります。
太陽光発電を取り入れてみる
個人宅で再生可能エネルギーを取り入れる方法として、太陽光パネルの設置もメジャーになってきました。2021年8月に政府が行なった有識者会議では、2030年時点で新築住宅の6割に太陽光パネルを設置することを目指すとしており、今後はさらに一般住宅での太陽光パネル導入が加速するものと考えられます。
導入の障壁となるのが費用面です。設置場所や発電量によって異なりますが、戸建て住宅で太陽光パネルを設置する費用相場は、100~200万円といわれています。
ただし、最近では初期費用をかけずに設置できるサービスも登場しています。主な方法は、次の3つです。
屋根貸し
自宅の屋根を設置業者に貸し出す方法です。設置費用を業者が負担するため0円になりますが、売電した収入はすべて業者のものになります。
ソーラーPPA
PPA業者が銀行や投資家から調達した資金を使って顧客の建物にパネルを設置する方法です。契約で定められた期間が経過すると、パネルの所有権は建物の所有者に無償譲渡されます。※
リース契約
リース契約でも自宅に太陽光パネルを設置することが可能です。一般的に、リース契約期間の終了にともなってパネルの所有権が契約者に移ります。※
※契約するサービスによっては対応が異なるケースがあります
まとめ
脱炭素は、近年世界中の国々で推進されている取り組みであり、もちろん日本も例外ではありません。日本は現在、年間で12億トンを超える温室効果ガスを排出しており、2050年までにこれをゼロにすることを目標としています。
また、これらの温室効果ガスの6割は、日常生活から排出されているという分析もあります。国や企業だけが取り組むべき問題ではなく、私たち一人一人の意識改革が必要なのです。
大がかりな取り組みでなくても、プラスチック製品を使わないといった小さな取り組みで十分です。脱炭素の実現に向けて、日頃のライフスタイルの見直しから始めてみてはいかがでしょうか。
▷関連記事
・車の脱炭素化とは?日本の目標や矛盾点は?EVやハイブリッド車についても解説
・脱炭素社会とは?日本国内での取り組みと、私たちにできること
▷グリラボSNSのフォローお願いします!!
Twitter @gurilabo
▷アイグリッドグループ